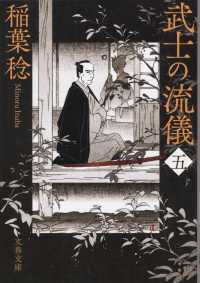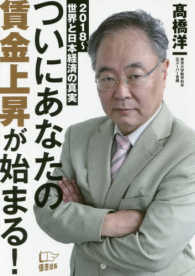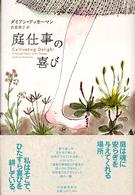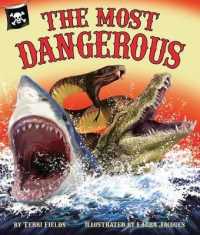内容説明
組織は一度は栄える。しかし必ず腐り始める。いつまでも俺が棟梁ではあかん。一番腐るのは上に乗ってるリーダーからや。今度は俺が席を譲る番や。「法隆寺最後の宮大工」西岡棟梁の後を継ぎ徒弟制度で多くの弟子を育て上げた鵤工舎の小川棟梁が、引退を機に後世に語り伝える、技と心のすべて。
目次
第1章 西岡棟梁との出会い
第2章 就業時代
第3章 鵤工舎
第4章 「育つ」と「育てる」
第5章 不器用
第6章 執念のものづくり
第7章 任せる
第8章 口伝を渡す
著者等紹介
小川三夫[オガワミツオ]
昭和22(1947)年、栃木県生れ。高校生のとき修学旅行で法隆寺を見て感激し、宮大工を志す。二十一歳のときに法隆寺宮大工の西岡常一棟梁に入門。唯一の内弟子となる。法輪寺三重塔、薬師寺西塔、金堂の再建では副棟梁を務める。昭和52年、独自の徒弟制度による寺社建築会社「鵤工舎」を設立。平成15年、「現代の名工」に選ばれる。平成19年、設立30周年を機に棟梁の地位を後進に譲り、引退する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
藤枝梅安
29
法隆寺宮大工・西岡常一さんの弟子、小川三夫さんが60歳を前にし、後進に後を譲る前に語った1冊。西岡棟梁の跡を継ぎ、その言葉も西岡棟梁の言葉そのまま。しかし、経験に裏打ちされた小川さん独特の軽妙さも感じられる。「三角定規の直角は信じない」で、直角を作り直す。(172ページ) ◆大工が集まったら「さしがね合わせをする」(173ページ)、オーケストラのピッチあわせを思い出す。 ◆大工の話だけでなく、日本文化の継承や日本の教育にまで話は及ぶ。2011/02/05
手押し戦車
9
困難を乗越え達成された自信に裏付けされた技が強くなる。経営や組織も人から教わった事を鵜呑みするのではなく自分の組織の状況に合う方法を考え解決していく。自分の技術や技能に囚われると周りが見えなくなってくるので行動しながら物事を修正して行き時代に適合する仕組みを作り上げていく。人を育てるとは右捻れの木があったら左捻れの木と組合せ時間が経つと強く組み上がる様に人の癖を見抜き強みを出せる癖を持つ人と組合せる。木の癖組みは工人の心組み。人に任せ人に譲る事で伝統の技を生きたものとして伝えていく。人に任せる大事さ2014/09/27
はれ
4
切ない。伝統文化とか技術の伝承とか、それをつくっている方々、つないでいる方々の想いの上でなんとか成り立っている。あやうい。棟梁、職人、勤め人それぞれ価値あり、それぞれ強みあり。近年、学校は、そつのない勤め人を育てようとしてきた。その中で個性と言い始め、小賢しい勝手人間が頭角をあらわすようになってきた。職人気質は弾かれがち。みなが気づきながら、表面的な居心地の良さにあまえてきた。もちろん私自身も。まずは己の考え、言動を改めねば。最後にある、棟梁の憂い。なんとかせねば。。2016/12/11
暴れ文屋
3
小川さん自身の語り口調で宮大工の仕事のこと、後継者のことを話しています。すんなり入ってくるけど、重みのある話が随所にありました。ときどき読み返したい本リストの1冊です。2008/12/15
とこまた
3
この本はいい本だ。頭でこねくり回した理屈じゃなく、体からひねり出された重みのある言葉で満ちている。齢39のオトコには堪える。何事も10年続ければモノになるというが、今の仕事に10数年。何をものしたのだろうかと一人凹んでしまった。2008/06/08