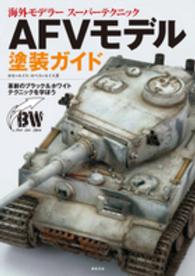出版社内容情報
初めて明かされる秘密!共同執筆現場の格闘。
『羅生門』『七人の侍』『生きる』…黒澤明の絶頂期をともにした稀有なシナリオ作家が、その凄まじい体験のすべてをここに書きつくした!
内容説明
戦後を代表するシナリオ作家、橋本忍はどのようにつくられたか。本書は、盟友・黒澤明との交友、葛藤を通じて描いた、すべての映画ファンに捧げる真に個性的な自伝である。
目次
プロローグ―東京行進曲
第1章 『羅生門』の生誕(傷痍軍人療養所の戦友;生涯の恩師・伊丹万作先生)
第2章 黒澤明という男(『羅生門』;『生きる』;『七人の侍』;『七人の侍』2)
第3章 共同脚本の光と影(ライター先行形;いきなり決定稿)
第4章 橋本プロと黒澤さん(二人の助監督;『影武者』;『乱』)
第5章 黒澤さんのその後
エピローグ
著者等紹介
橋本忍[ハシモトシノブ]
1918年、兵庫県神崎郡市川町に生まれる。鉄道教習所を経て応召入隊中に結核にかかるが、その療養中シナリオにはじめて接して伊丹万作に師事、脚本家を志す。1950年、『羅生門』を監督する黒澤明との共同脚本でデビュー。『私は貝になりたい』(59年)では監督にも取り組み、三作品を監督した。1973年に橋本プロを設立、製作者として『砂の器』『八甲田山』の大ヒット作を送り出す。上記のほか主なシナリオ作品に『真昼の暗黒』『張込み』『切腹』『白い巨塔』『上意討ち―拝領妻始末―』『日本のいちばん長い日』などがあり、戦後の日本映画界を代表する脚本家である(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
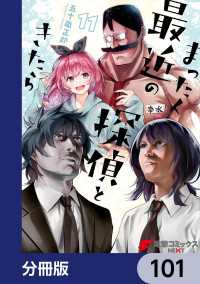
- 電子書籍
- まったく最近の探偵ときたら【分冊版】 …
-
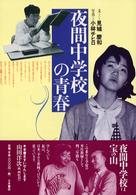
- 和書
- 夜間中学校の青春