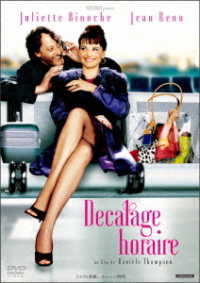出版社内容情報
あの「田中角栄研究」「淋しき越山会の女王」はじめ、昭和四十六年以降の大変動期、日本をうつしとった時代の一級証言と手記の数々
内容説明
「文芸春秋」誌上を飾った時代の一級証言から精選・再編集。当事者が語る激動の歴史、昭和46年~62年完結。
目次
重信房子の父として(重信末夫)
蓮見喜久子・過去からの証人(沢地久枝)
小野田少尉発見の旅(鈴木紀夫)
田中角栄研究―その金脈と人脈(立花隆)
内側からみた紅白歌合戦(小幡泰正)
新潟三区で立候補するの弁(野坂昭如)
東京サミット大江戸警備日記(山田英雄)
闘病日記・最後の7日間(石原まき子)
昭和史の中の魔物(司馬遼太郎)〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぽてちゅう
14
「小野田少尉発見の旅」(鈴木紀夫著)を探していたら、この分厚いの(733p)が出てきた。レビューが2018年で止まっているあたり読む壁の高さを感じる。本命は14pほどだがタイトル下に「*」が。何かと思えば部分削除で掲載していると。取り寄せ確定。鈴木さんが小野田少尉に声をかけられたのが昭和49年。戦後すら過去で前へ突き進んでいた時代に「上官の命令なくば帰還できぬ」となお戦時中の軍人がいたとは。その他は拾い読みだが、昭和の各界で活躍した特異な体験をした当事者が語る証言集は、読み応えがあり思わぬ拾い物であった。2024/04/09
Mr.deep
1
やっと読み終えた!3巻に入ってほぼ半年、第1巻からだと足かけ5年の長期戦。その感動で感想はほぼ吹っ飛びました。「わたしの憂国記」「重信房子の父として」「小野田少尉発見の旅」辺りは印象に残ってます2018/09/02
rbyawa
0
h086、大雑把に高度経済成長期とその歪みのところまでで、いわゆる大学闘争などまでが扱われていて要するに学生側が戦後世代、対峙する学校側が戦前世代であるということがところどころで察することが出来る。医師のインターン制を契機にした東大闘争は正直なところ、まあまともには制度が扱われないのだろうという意味で今見ると学生の側のほうが正しく、ただ確かにやり方には非合法なところが目立ち応援するわけにはいかない、どちらの立場もわかる。しかし、1巻からそうだったがこの国の皇室の人々って本当に真っ当だよね…勿体無いくらい。2017/12/15
ささ
0
■興味深く読んだのは、『わたしの憂国』(横井庄一氏)、『重信房子の父として』、『小野田少尉発見の旅』(鈴木紀夫氏)、『淋しき越山会の女王』(児玉隆也氏)、『女王陛下の握手』(野村忠夫氏)、『ワシントンの空は青かった』(入江相政氏)、『五つ子の父としての一年間』(山下頼充氏)、『ジャイアンツと私』(長嶋茂雄氏)、『国語審議会委員への公開状』(市原豊太氏)『公開状』における、当用漢字を決めた方法が、東南アジアを征服した際、そちらの人たちに通じるよう、新聞や通達に必要な漢字を選んだ結果らしいという説には納得。2013/05/20