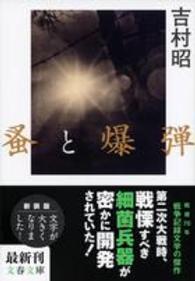- ホーム
- > 和書
- > 社会
- > 社会問題
- > マスコミ・メディア問題
出版社内容情報
昭和40年のはじめ、明日の新聞はコンピューターによって作られると確信している男がいた。60年代に朝毎読日経、新聞社の勝負を決した経営戦略の差を描く千五百枚
内容説明
技術後進企業が遅れを取り戻し、トップに立つためには何が必要だったか。ひとつの時代が去り、新しい次の時代が押し寄せてくる、その変り目にあって時代の先を読んだ人々と企業のドラマ。
目次
第1部 黎明
第2部 決断
第3部 始動
第4部 試練
第5部 明暗
第6部 離陸
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
206
第17回(1986年)大宅壮一ノンフィクション賞受賞。 日経・毎日のコンピュータ導入の取り組みを 重厚な筆致で描く。 「活字が消える」という事の重みは 新聞社で生きた人々にしか わからないこと なのだろう。 三島事件、IBM、毎日新聞社倒産など 時代背景をふんだんに 盛り込みながら、 技術革新が かつての新聞社の風景を激変させた 過程を綿密な筆致で描く、良書である。2017/05/15
スプリント
9
新聞が活版印刷からコンピュータで作成される転換期について書かれた本です。大手新聞社のコンピュータ化の取り組みと並行して沈没していく毎日新聞を軸とした新聞業界の事件史が書かれているのも興味深いです。時々読み返したくなる本です。2018/07/29
つっちー
2
コンピュータという機器が、未だ市民権を得ていなかった時代の、大手新聞社二社、日経と毎日の技術革新への取り組みを主軸に、マスメディアの興亡を描いた力作です。まさに、コンピュータ版解体新書、ターフェルアナトミアと呼ぶに相応しい一冊でした。
kozawa
2
1980年代半ばに見た、主に戦後の日本の新聞の歴史。朝日新聞のファクシミリ導入から日経・朝日の活字追放(IBM機導入)を軸に新聞に切り込んでいく。かなり面白いが、今にして思えばこういう描き方ってどうなのか、という疑問もあり。また何十年かすると本書が描いた世界は実感されなくなっていくのだろうか。2010/10/14
い
1
時代の最先端を走っていなければならないはずの新聞社が、気がついてみたら一番遅れてたということにもなりかねない。→なっている。2021/10/07