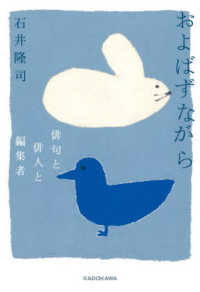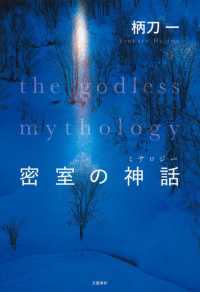出版社内容情報
言葉というのは実に奥の深いものです。私たちは普段、何気なく言葉を使っていますが、その裏側にはさまざまな微妙なニュアンスが込められていて、使い方を間違えると、不自然な感じを与えたり、誤解を生じたりします。商学部で教鞭をとっていた同志社大学名誉教授の著者は、中学生時代、稀代の言語学者・国語学者である時枝誠記の本と出会いました。時枝は、現代の記号論の祖・ソシュールの言語理論を真っ向から批判したことで有名ですが、著者はこの時枝との出会いを契機に、言葉への関心を深めます。最近、時枝を再読した著者は、時枝の考え方からいろいろと影響を受けていることに気づいたそうです。本書は、そうした著者による、日本語、特に「喜」「怒」「哀」「楽」などの感情を表わす言葉をめぐるエッセイを収めたものです。例えば、よく「不憫」という言葉が使われるが、それはどういう思いであり、どういうケースで用いられるのか、「怒(いか)る」と「怒(おこ)る」と「憤る」には、どういうニュアンスの違いがあるのか等々、時枝理論を咀嚼して「喜怒哀楽」の奥に潜むさまざまな感情に分け入り、その綾を探究し、日本語の精緻な構造に迫ります。言語学の知識をもとに言葉の神秘にいざなってくれる本書は、言葉に興味をもつ人なら存分に楽しめること請け合いです。
内容説明
「言葉の奥に潜む気持ち」を探る!「不憫」とはどんな思いか、「怒る」と「怒る」と「憤る」にはどういうニュアンスの違いがあるのか等、「喜怒哀楽」を表す言葉の奥に潜むさまざまな感情に分け入り、日本語の精緻な構造に迫る。
目次
1 不憫
2 喜
3 怒
4 哀
5 楽
補遺 感情表現としての言語―時枝誠記の「言語過程説」に基づく「喜」「怒」「哀」「楽」
著者等紹介
瀧田輝己[タキタテルミ]
1948(昭和23)年生まれ。慶應義塾大学商学部卒業。同志社大学商学部教授、同志社大学大学院商学研究科博士後期課程教授を経て、同志社大学名誉教授、博士(商学)(慶應義塾大学)、公認会計士、税理士、エッセイスト(日本ペンクラブ会員)。この間、日本会計研究学会理事、日本監査研究学会理事、日本簿記学会理事、税理士試験委員、学会賞審査委員(日本会計研究学会)等を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。