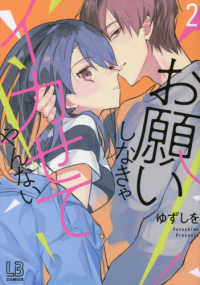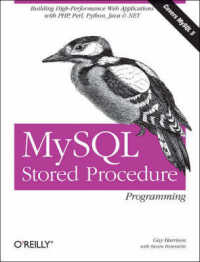内容説明
“フィナンシャル・タイムズ”“カーカス・レビュー”年間ベストブック!名著『国家はなぜ衰退するのか』をしのぐ傑作。自由の命運を左右する「狭い回廊」への道は一様ではなく、またそこに留まるのも容易ではない。成長著しい中国の繁栄に潜む罠、世界最大の民主主義国と言われながら、カースト制度という見えない「規範の檻」に縛られたインド、アメリカ合衆国のアンバランスな発展の功罪、南米やアフリカの能力を欠いた「張り子のリヴァイアサン」たち、「足枷のリヴァイアサン」が制御不能に陥ったナチス・ドイツと現代のポピュリズム運動との連続性、幅広い連合の形成によって「狭い回廊」内への移行に成功した日本や南アフリカと、失敗したトルコやジンバブエ―。さまざまな歴史の教訓から浮かび上がるリヴァイアサンの統御法と回廊内に留まるすべとは?ノーベル経済学賞の受賞が有力視される経済学者と気鋭の政治学者が20年におよぶ研究をもとに贈る渾身の書。
目次
第8章 壊れた赤の女王
第9章 悪魔は細部に宿る
第10章 ファーガソンはどうなってしまったのか?
第11章 張り子のリヴァイアサン
第12章 ワッハーブの子どもたち
第13章 制御不能な赤の女王
第14章 回廊のなかへ
第15章 リヴァイアサンとともに生きる
著者等紹介
アセモグル,ダロン[アセモグル,ダロン] [Acemoglu,Daron]
マサチューセッツ工科大学(MIT)エリザベス&ジェイムズ・キリアン記念経済学教授。専門は政治経済学、経済発展、成長理論など。40歳以下の若手経済学者の登竜門とされ、ノーベル経済学賞にもっとも近いと言われるジョン・ベイツ・クラーク賞を2005年に受賞。ほかにアーウィン・ブレイン・ネンマーズ経済学賞(2012年)、BBVAファンデーション・フロンティアーズ・オブ・ナレッジ・アワード(経済財務管理部門、2016年)など受賞多数
ロビンソン,ジェイムズ・A.[ロビンソン,ジェイムズA.] [Robinson,James A.]
シカゴ大学公共政策大学院ハリススクール教授。ハーバード大学教授などを経て現職。専門は政治経済学と比較政治学、経済発展と政治発展。ボリビア、コンゴ、シエラレオネ、ハイチ、コロンビアなどで実証研究を行なっている
櫻井祐子[サクライユウコ]
翻訳家。京都大学経済学部卒業、オックスフォード大学大学院で経営学修士号を取得。訳書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
ころこ
よしたけ
sayan
ta_chanko