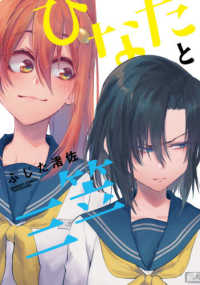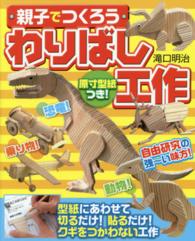目次
1 哲学・金・音楽(1900~1930)
2 夜にひびく黒い声(1930~1950)
3 ニュー・ニグロ(1950~1965)
4 ブラック・イズ・ビューティフル、そして混乱(1965~1970)
5 企業時代の救いの歌(1971~1975)
6 クロスオーヴァー―リズム&ブルースの死(1975~1979)
7 同化の功績、レトロヌーヴォの台頭(1980~1987)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たまきら
39
読み友さんに勧められて。1988年原著出版、アフリカ系アメリカ人の歴史を、音楽を軸にして綴った骨太な一冊です。そして私と同様骨太の音楽がお好きな方と見受けられる作者さん、私好みが一緒なので同じことに心を痛めました。複雑に織りなす人種・貧困・男女差別にまで目が届いていない気もしますが、80年代後半の視点だしなあ。彼の言う「死」がブラックがベージュとなることにあるのだとしたら、ブラックミュージックを愛するアジア人としては少々悲しいです。同胞愛は素晴らしいけれど、文化の隔離政策には納得できないもの…。2025/07/07
kj54
4
原著は、1988年刊行。それまでの20世紀ブラックミュージック産業の歴史。ピーター・バラカン(解説収録)曰く「珍しく黒人の評論家が書いた」本。本編の冒頭に、黒人の白人社会に対する「同化」と「自己充足」という2項対立が提示される。両方ともに必要なことは勿論。しかし、限定的な経済的豊かさ(中産階級化)や、漠然としたアメリカ人としてのアイデンティティと引き換えに、R&Bの力を弱めてきたと著者はいう。米国のラジオ業界になじみが薄く、その部分はとっつきにくかったが、読みやすくミュージシャンに対する評論も楽しい。名著2022/06/24
Neishan
3
ブラック・ミュージックのことを、黒人自身が語ったり、分析する本というというのが刊行当時(80年代)には珍しかったということを踏まえつつ読んだ。ミュージシャンやレコード会社といった上流だけでなく、ラジオ局やレコード店など音楽業界全体を視野に入れ、調べ、聞いたことを克明にまとめており、貴重な資料だと思った。著者によるプリンスとマイケル・ジャクソンに対する認識は興味深い。見た目の印象は辛辣に批評しても、音楽的にはその功績を認めている。そのギャップが面白かった。2022/08/09
doji
3
とにかく膨大な知識と取材に基づいた正史は読み応え十分。これまでロックミュージックとしての時間の流れに馴染みがあったため、虐げられた視線からのジミ・ヘンドリックスや、ブラックミュージックからみたマイケル・ジャクソンやプリンスの異端性など、興味深い視点がたくさんあった。2016/11/10
らばだ
3
黒人である著者から見た黒人音楽の興隆と衰退を圧倒的なデータ量で著述。彼の視点が白人評論家と明らかに一線を画す点は、ミュージックシーンで起きるあらゆる事象を、黒人コミュニティに利益をもたらすか否かで判断する点だ。エルヴィスの素質を認めながらも愛情の無い評価、チャック・ベリーを白人にそそのかされて間違った道を歩んだとする評し方、ジミヘンに黒人コミュニティがいかに冷ややかな視線を向けたかの記述等は新鮮で、真にブラックミュージックを愛する人なら読まずにはいられない一冊。2014/12/04
-

- 和書
- ズーム! (新訂版)