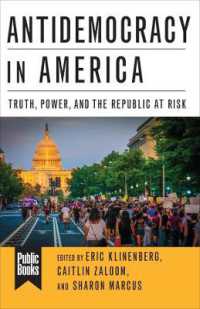内容説明
現代演劇の父、岸田國士の戯曲選集刊行開始。劇に何が語られているかを問うことは、かならずしも劇それ自身の美を問うことではない。劇が劇であるためにまず何よりも大事なのは、劇の言葉である。つまり劇的文体。岸田國士はこれを「語られる言葉の美」といい、「非」劇の言葉こそ問題なのだと明言した。
著者等紹介
岸田國士[キシダクニオ]
1890年(明治23年)東京・四谷生。劇作家、小説家、評論家、翻訳家、演出家。陸軍士官学校を卒え少尉に任官したが、退役。東京帝国大学仏文選科に学び、フランス演劇への興味を深め渡仏。ジャック・コポーのヴィユ・コロンビエ座やジョルジュ・ピエトフの一座に出入りし、同時代ヨーロッパの芸術革命の波に触れて1923年(大正12年)に帰国。「劇作」の創刊、久保田万太郎、岩田豊雄とともに文学座を創設。戦後は1950年に結成の雲の会に文学立体化運動を提唱するなど現代演劇の理論的指導者としても多大な業績を残した。53年日本芸術院会員。翌54年「どん底」演出、舞台稽古中に倒れ急逝。岸田國士戯曲賞は、新人劇作家の登龍門として知られる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モルテン
7
凄い。登場人物の感情、人間関係、心理的距離、それらを簡素な日常会話で浮き彫りにしてしまう。しかも、これらの戯曲が発表されたのが1920年代! 『紙風船』、最初、すれ違っている夫婦の話かと思いきや、終盤で互いに愛情を持っていながらそれをうまく表現できない夫婦の話と分かり、でもそれはつまりすれ違っているってことだよな、と思いつつ、ラスト、そうか、この話は、どんなに近くにいてもやっぱり人は皆一人で孤独なのだということを表現しているのだと気づいた。 『温室の前』、チェーホフの『ワーニャ伯父さん』に影響受けている?2014/01/09
Miss.W.Shadow
3
演出によって相当味が違うだろうなという所に古典の風格。すごく楽しそう。空気感をどう取るかが重要。2011/11/03
kuboji
1
恋愛恐怖病、屋上庭園、紙風船、ぶらんこ、驟雨、秘密の代償…いずれも良かった。説明のためだけの無駄なセリフがなくて、背景や心理を読み取ろうとするものの、はっきりわかるわけではないから尾を引く。だいたいわかりやすい盛り上がりはないので、ここで終わるのか!というものが多い。戯曲としてはとてもおもしろいけれど、これを舞台で面白く見せるのはかなり難しそう。すごくいい劇になるか、時間の無駄だったと思うものになるかのどちらかじゃないだろうか。映像・マンガのほうがやりやすそう。2019/05/17
AnoA
1
命を弄ぶ男ふたり(1925)/ぶらんこ(1925)/紙風船(1925)/葉桜(1926)/恋愛恐怖病(1926)/驟雨(1926)/屋上庭園(1926)/賢婦人の一例(1927)/温室の前(1927)/明日は天気(1928)/頼母しい求縁(1930)/ここに弟あり(1931)/秘密の代償(1933)2015/10/29
kino
1
言葉の背後にある何倍もの気持ちが間に滲む。「葉桜」しみじみ。2011/11/19
-

- 電子書籍
- 週刊ビッグコミックスピリッツ 2022…
-
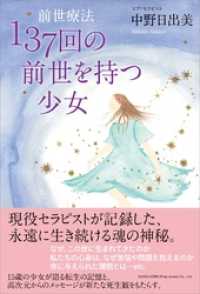
- 電子書籍
- 前世療法 137回の前世を持つ少女
-

- 電子書籍
- 少年名探偵 虹北恭助の冒険 講談社ノベ…
-
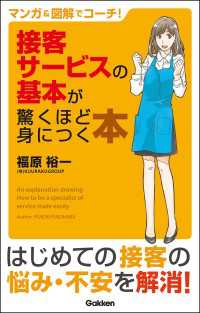
- 電子書籍
- マンガ&図解でコーチ!接客サービスの基…