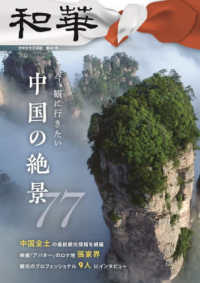内容説明
イスラム主義の気運の高まりを警戒する勢力によって、国民劇場での夕べは流血の惨事と化した。イペキとの未来を望みうるのかどうか悩みつづけるKaも、一連の騒動に巻き込まれ、俳優スナイ・ザイムや“群青”をはじめとする人々の思惑に翻弄されていく。大雪によって外部から切り離された地方都市カルスで、詩人が対峙することになる世界とは。政治と宗教の対立に揺らぐ現代トルコを緻密な構成で描いた世界的ベストセラー。
著者等紹介
パムク,オルハン[パムク,オルハン][Pamuk,Orhan]
1952年、イスタンブル生まれ。イスタンブル理工大学で建築を学んだ後、イスタンブル大学でジャーナリズムの学位を修得。その後、コロンビア大学客員研究員としてアメリカに滞在した。1982年発表のデビュー作『ジェヴデット氏と息子たち』(未訳)がトルコで最も権威のあるオルハン・ケマル小説賞を受賞。その後に発表した作品もトルコ、ヨーロッパの主要文学賞に輝き、世界的な名声を確立する。1998年発表の『わたしの名は赤』(ハヤカワ文庫)は世界の有力紙誌で激賞され、国際IMPACダブリン文学賞を受賞。2002年発表の『雪』も同様の高評価を受け、2006年にはノーベル文学賞を受賞した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NAO
89
イスラム主義と欧化主義の対立。貧しさゆえに宗教にすがる人びとと、国の政教分離政策。神を信じるか信じないかという論争。こういった現代のイスラム社会の内情を描いた作品は数少なく、この作品は、イスラム原理主義が貧しい下層階級の中でどのように浸透していくのかということを理解するうえでとても興味深い。異なる文明との出会いと共存。貧しさの中で近代化、西洋化が進んでいくとき、自分たちの国、自分たちの文化、自分たちの宗教をどのようにして守っていくかということは、自分自身のアイデンティティを守るということでもあるのだ。2020/12/22
やいっち
82
訳者のあとがきによると、オルハン・パムク最初で最後の政治小説と銘打たれているとか。となると、本書で著者の文学を評価するのは危ういのかもしれない。それでも、力量はしっかり感じることができた。一方で、上巻での感激ぶりに比べ下巻はややトーンダウンの感が否めなかった。2019/08/21
藤月はな(灯れ松明の火)
63
「群青」を救うために舞台でスカーフを脱ぐことを遠回しに強要するKaにカディーフェが糾弾する場面に胸を抉られます。民主主義がなく、戒律に縛られるイスラム文化圏を「可哀想」と見るのも、個人の痛みも苦しみも想像して理解したと思い込むのは簡単だ。しかし、それはその文化圏の人々の立場に立っていないからこそ、できる一種の傲慢にしか過ぎない。その傲慢さをドイツ(西欧)でも異邦人でしかなかったKaが行うということが痛烈な皮肉となっている。Kaの軌跡をなぞっていく主人公や読者にこの言葉が投げかけられる。「お前に何が分かる」2014/10/25
nobi
59
オルハンの視点で語られる主人公Kaの心情を生々しく感じたとは言えない。ただ会話主体のその会話は緊張感を孕んでいる。相手の表現表情仕草が何を示唆しているのか誰もが忖度を迫られている。心通った会話であったはずが直後に銃を突きつけられる。神を信じるあり方も信じないあり方も民族宗派主義…の数だけありどこに属するかは巡り合わせで決まるように見える。「遠くにいては僕らのことはわかりっこないんだから」と釘を刺されていても、貧困と分断による苦渋と西欧への敵愾心の諸相に触れ得る。部外者として留まることを許さない厳しさにも。2017/03/20
えりか
55
カルスの混沌、貧困とは関係なく舞い落ちる雪の幻想と現実の過酷さが対比となって心に刻まれる。共和・世俗主義とイスラム主義の対立。過激なクーデター。他者を武力行使で否定する。「私はこう思う。故にあなたもこう思うべき(力ずく)」が出来上がる…。kaも愛と幸せのために両者に巻き込まれながら奔走する。kaだけ妙に自分本位のように思えてならなかったのだけど、愛のため、思想のため、主義のために戦うことにどこに違いがあるのかと思い直す自分もいる。彼の悲壮と彼の絶望がカルスの街と重なり、救いのない雪の静けさだけが心に残る。2018/02/02
-

- 電子書籍
- 潰れる家門の契約公女になりました【タテ…