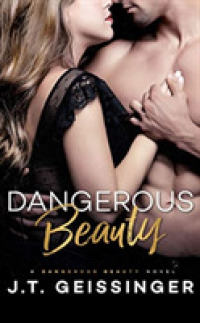出版社内容情報
生命の心は、脳と身体と世界の相互作用から創発する。認知科学の第一人者が、微生物や人工生命などの例を交えて提起する心の科学
内容説明
ゴキブリは尾角で検知した風速から敵を峻別し逃走を図る。粘菌アメーバは餌が尽きると個々の生物から移動する集団生物へと姿を変える。生きるための選択は外からの情報に支えられており―人間が言語を足場として世界を広げるように、生命の心は閉じた形ではなく、自己と環境の相互作用から創発する。認知科学の第一人者が知性に対する見方を革新し、人工知能やロボット、人工生命研究に多大な影響を与えた記念碑的名著。
目次
イントロダクション―ゴキブリの脳を載せたクルマ
1 外なる心(自律的なエージェント―月面を歩く;状況に置かれた幼児;心と世界―移ろう境界;集合の叡智、粘菌流;幕間―これまでの概略)
2 外に広がった心を説明する(ロボットを進化させる;創発と説明;神経科学的なイメージ;存在する/計算する/表象する)
3 前進(心とマーケット;言語―究極の人工物;心、脳、それとマグロの話―塩水に浸かった要約)
エピローグ―脳は語る
付録 エジンバラ大学哲学教授、論理学・形而上学講座主任教授アンディ・クラーク氏による講演とディスカッション
著者等紹介
クラーク,アンディ[クラーク,アンディ] [Clark,Andy]
1957年生まれ。哲学者。サセックス大学教授。心の哲学、認知科学の第一人者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ばんだねいっぺい
原玉幸子
mim42
武井 康則
人生ゴルディアス