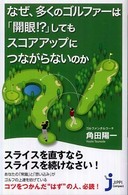出版社内容情報
チューリングが構想しフォン・ノイマンが実
現したコンピュータ開発の「創世記」と天才
達が集ったプリンストン高等研究所の全記録
推薦/森田真生
ジョージ・ダイソン[ダイソン ジョージ]
吉田 三知世[ヨシダ ミチヨ]
内容説明
科学者たちがコンピュータ開発を成し遂げられたのは、学問の自由と独立を守るプリンストンの高等研究所という舞台あればこそであった。そこでフォン・ノイマンはどう立ち回り、アインシュタインやゲーデルを擁した高等研究所はいかにしてその自由性を得られたのか。彼らの開発を支えた科学者・技術者はどのように現代に直結する偉業を成し遂げたか。大戦後の混乱に埋もれていた歴史事情を明らかにした大作。
目次
第10章 モンテカルロ
第11章 ウラムの悪魔
第12章 バリチェリの宇宙
第13章 チューリングの大聖堂
第14章 技術者の夢
第15章 自己複製オートマトンの理論
第16章 マッハ九
第17章 巨大コンピュータの物語
第18章 三九番めのステップ
著者等紹介
ダイソン,ジョージ[ダイソン,ジョージ] [Dyson,George]
アメリカの科学史家
吉田三知世[ヨシダミチヨ]
京都大学理学部物理系卒業。英日・日英の翻訳業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。