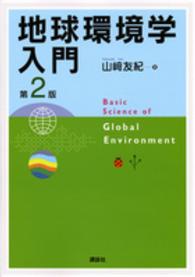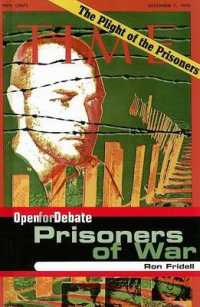出版社内容情報
砲から精密機械まで欠かせない優れ物の起源と進化を探る歴史読み物。
内容説明
水道の蛇口から携帯電話まで、日常生活のそこここに顔を出すねじ。この小さな道具こそ、千年間で最大の発明だと著者は言う。なぜなら、これを欠いて科学の精密化も新興国の経済発展もありえなかったからだ。中世の甲冑や火縄銃に始まり、旋盤に改良を凝らした近代の職人たちの才気、果ては古代ギリシアのねじの原形にまでさかのぼり、ありふれた日用品に宿る人類の叡智を鮮やかに解き明かす軽快な歴史物語。
目次
第1章 最高の発明は工具箱の中に?
第2章 ねじ回しの再発見
第3章 火縄銃、甲冑、ねじ
第4章 「二〇世紀最高の小さな大発見」
第5章 一万分の一インチの精度
第6章 機械屋の性
第7章 ねじの父
著者等紹介
リプチンスキ,ヴィトルト[リプチンスキ,ヴィトルト][Rybczynski,Witold]
スコットランドのエディンバラ生まれ、両親はポーランド系。カナダのマギル大学で建築学の修士号を取得。現在、ペンシルベニア大学教授として、建築学や都市論を講じる。住宅から技術文化一般までを扱った著書多数。受賞歴も多く、2007年には、米国立建築博物館が主催するヴィンセント・スカーリー賞を受けている
春日井晶子[カスガイアキコ]
英米文学翻訳家、東京外国語大学卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
259
サブタイトルに「この千年で最高の発明をめぐる物語」ってあるね。著者さんは、自宅を手作りしたそうです。そんな彼の元に道具に付いてのショートエッセイ執筆依頼が来て。道具箱を見てみると、起源は古代に遡る物ばかりだったそうな。千年に限ると……と奥さんに相談したらねじ回しを提案され、調べてみたら面白かったって事みたいですが。ねじとねじ回しは我々の社会技術をひっそりと支えてくれていますが、最高の発明なのかなぁ。別の代替手段はありそうですよ。そして最後はアルキメデスに「ねじの父」の称号を贈ると。コ、コンセプトが😅。2025/08/21
KAZOO
117
確かにこの題材は楽しいもので、今までの最高の発明なのでしょう。ねじとねじ回しがなかったらと考えるとかなり大変であったと思われます。ただ広く浅くというような感じで一通りの知識は得ることはできるのですが、もう少し最近の状況などを深掘りしてくれてもいいと感じました。これとは別ですが、日本ではかなり昔からねじや釘を使わない建築や工作物があったのでその関連も知りたい気がしました。2017/11/21
へくとぱすかる
57
この1000年間の最大の発明と言える道具は何か、という問いかけに、著者は探求を始めた。タイトルにありながら、その道具とは何かが、中身に書かれていない! もちろん著者は「ねじ」だ、と言いたいに違いないが、途中で「ねじ」とは何なのか、という定義の問題が割り込んでくる。いわゆる「木ねじ」に限ると、発明は古代にはさかのぼらないが、広い意味で考えれば……というわけ。2016/06/23
エディン
22
この1000年の最高の発明品を探して、ねじとねじ回しについて語られている。歴史も数学も苦手なもので、分からないところは飛ばし読み。ただ、どこにでもある、家にもいくつもある、ねじとねじ回しが意外にすごいものである、というのは目から鱗...ボタンもすごい発明品として、書かれていたのも興味深い。2020/04/04
すーぱーじゅげむ
18
「この千年で最高の発明は何か」雑誌に原稿を依頼されたのをきっかけに、ねじとねじ回しの歴史を追った作品です。各地の図書館を訪ね、美術館では宗教画にドライバーが描かれていないか虫眼鏡で調べ、係員に怪しまれ。知的好奇心を刺激する連作エッセイ。通勤本に最適でした。必要は発明の母の場合と、何の役に立つか分からないけれど天才オタクが開発しちゃったパターンがあるみたいです。図や絵がたくさん入っていて、工具に詳しくなくても分かりやすかったです。正確なねじを作るには正確に回る旋盤が必要、それを作るのに正確なねじが必要。2024/03/22
-
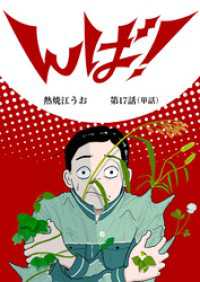
- 電子書籍
- んば!【単話】(17) ビッグコミックス