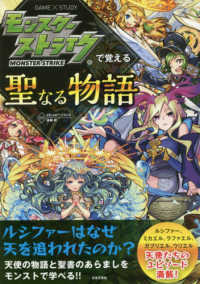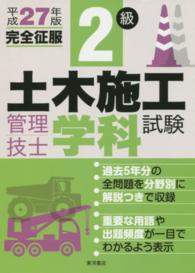内容説明
第二次大戦前夜、ヒトラー・ドイツは機甲部隊と急降下爆撃機による特異な戦術を編み出した。ブリッツクリーク(電撃戦)と呼ばれたこの作戦こそ、ドイツの緒戦の大勝利をもたらす近代戦術の劇的な転換点となる。デイトンはその本質を1940年5月の対フランス戦に見出し、軍事テクノロジーの飛躍的発展とドイツ伝統の軍事思想を詳細に検討し、電撃戦の全貌をいきいきと描破した。精緻かつ臨場感溢れる戦史ドキュメントの傑作。
目次
第1部 ヒトラーとその軍隊
第2部 戦争するヒトラー
第3部 電撃戦―その武器と方法
第4部 ムーズ川をめぐる戦い
第5部 ひびの入った勝利
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イプシロン
29
「電撃戦」と聞けば速戦即決を思い浮かべる人が多いのだろうが、デイトンの見解はそれとは異なる。ある条件がすべて整ったときだけ起こる必然的な戦術が電撃戦だというのだ。これはある種、条件が整ったときに必然の結果が起こるという仏教の思想に非常に近いといえる。本書がww1以降の欧州の歴史や政治的背景、地理地形、気候風土、はたまた各国民のものの考え方といった電撃戦が起こる諸条件を列記し詳細に記しているのがその証左といえよう。そうした条件の中で最大の要因となるのが、政治的指導者の出現とその指導者への支持にあると読めた。2018/12/20
緋莢
19
<ブリッツクリーク(電撃戦)という言葉は、一九三九年九月、ドイツ軍がポーランド西部をまたたく間に包囲して以来、広く使われるようになった>ドイツに緒戦の大勝利をもたらし、近代戦術の劇的な転換点となったブリッツクリーク(電撃戦)。そこには、ハインツ・グデーリアンという 大きな存在がいて…<一人の人間が、ある兵器の設計に影響を与え、それを使用する兵士たちの訓練をとりしきり、 攻撃計画立案に参与し、さらに自ら兵を率いて戦闘に参加したというのは(続く2024/10/14
Cinejazz
16
ヒトラ-の出現からダンケルク陥落までの、ドイツ国防軍の機甲部隊と急降下爆撃機による “ブリッツクリ-ク(電撃戦)” と呼ばれた、1940年5月の対フランス戦の全貌を精緻かつ臨場感溢れる筆致で描かれた、レン・デイトンの戦史ドキュメント。 ・・・〝ヒトラ-の没落を招いた種々の要因の第一は、彼のユダヤ人に対する謂れのない憑かれたような憎悪である。科学の分野に限って言えば、ユダヤ人迫害によって、切実に必要としていた軍事技術を失った。ナチ体制が反ユダヤ政策をとらなければ、恐らく1930年代末頃まで↓2024/01/09
植田 和昭
12
始めは読みにくいなあと思っていたのですが、第2部あたりから快調に読み進んで読了。ポーランド戦も電撃戦かと思っていたのですがフランス戦だけが唯一の電撃戦だった。陸軍大国フランス、文化と芸術の国そして食文化の国フランスは完膚なきまでにドイツに叩きのめされます。硬直した第一次大戦型のフランス軍は、ドイツ軍の圧倒的スピードについていけず、大敗を喫します。プライドばかり高いフランス軍はドイツ軍の前にはまったく歯が立ちません。もしダンケルクで完全勝利をおさめていたならイギリスも降伏せざるを得なかったでしよう。2024/09/13
CTC
12
94年ハヤカワ文庫NF版刊、単行本は89年同社、原著は79年刊。著者は英国では「スパイ小説の巨匠」とされる作家だが…とにかく本書は文句なしに面白いノンフィクションだ。本国の関係者だけでなくグデーリアンの参謀長を務めた独ネーリング大将や蘭・米の指揮官らへの取材により広範な事実の把握・提示がなされている。永く読み継がれるだけのことはあるなと感服したしだい。 著者には空軍服務経験もあるが、美術学院を出ていて鉄道保線員や縫製工場主任等の職歴がある。これらが厚みある著述を担保しているのだろう。2023/04/22
-

- 洋書
- Sudden Death