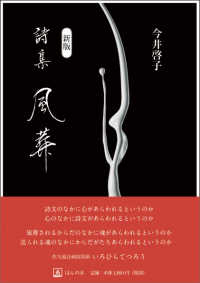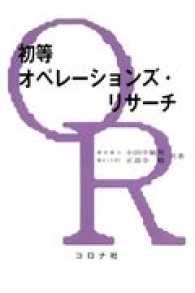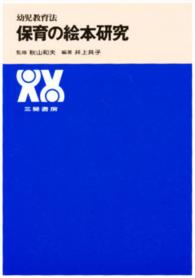内容説明
宇宙を愛し、海を愛する現代SF界の巨匠クラークがさがしあてた地上の楽園、スリランカ。彼はこの伝説に彩られた美しき島を拠点に、持前の軽妙でユーモアあふれる語り口をもって、世界各地で科学解説・啓蒙活動をくりひろげてきた。宇宙計画の将来は?真空中で人は生きのびられるのか?地球外生命の可能性は?2001年の世界は?本書はこういった疑問に答える科学エッセイのほか、最愛の地スリランカでの生活点描、難破船の財宝引揚げをめぐる海洋冒険譚など60~70年代のクラークの活躍をあますところなく伝える自伝的エッセイ集である。
目次
セレンディピティ(Serendipity―堀出しもの)のこと
宇宙時代の夜明け
使用人の問題―東洋的流儀
財宝の香り
運行する星々
宇宙をさぐるには
新鮮な真空のひと呼吸
2001年の世界
「いま、月はふたたび生命を…」
〈タイム〉誌と〈タイムズ〉紙
これからの二十年
衛星とサリー
シンドバッドの海
ウイリーとチェズリー
水星と人間の心
オリンポスの雪
アイザック・アジモフ紹介の辞
宇宙の生命
UFOに関する最後の(?)発言
「むかむか」の来襲
クラーク条令
科学技術と知識の限界
宇宙科学委員会
電話の新世紀
アユ・ボワン!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roughfractus02
8
1956年にスリランカに居を定めて20年を超えて、作者はSF作家として歩んできた過去を振り返る、と言えば本書は単に回顧録や自伝エッセイと呼ばれるだろう。が、スリランカから世界を眺められるのは、彼の居住する「エレクトロニック・コテージ」が、第二次大戦時にレーダー技師として自ら考案しその後実現した通信衛星によって、世界中のネットワークと繋がっていたからだろう。科学技術で基礎付けられた海洋と宇宙を巡る楽観的なSF観の作者だが、他民族国家インドで通信システムによる教育に科学技術を活用する場面では実践的に見える。2023/10/24
山像
1
1970年代までのクラークの未来予測は驚くべき先見性があったり楽観的過ぎたり幅があるが、総じて「SFのイマジネーションが未来を創造する」という広義の楽観主義が見て取れ、とても心地良い(この観点には個人的にはあまり賛同できないけれど)。 クラークの小説で「未来社会では教育が人類の理性を後押しして多くの社会問題は解決された」みたいな描写が出てくる度に流石に楽観も度が過ぎるんじゃと思ってたんですが、なんとインドで通信衛星を使った教育システム構築に関わるなどしてたのですね。そこまでガチなら何も言えることはない…。2016/04/16
meg
0
クラークがカール・セーガンと接点があったことをこの本で知り、カール・セーガンによって宇宙への興味を駆り立てられ、クラークによってSFの面白さを知った私にとっては、まさに掘り出しもの(セレンディピティ)の本でした。2014/08/31