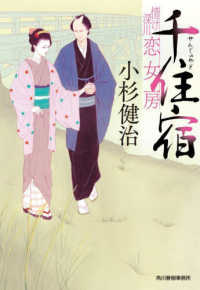内容説明
ミュンヘン・オリンピックのテロ事件の犯人に報復するべく、ユダヤ人グループは立ち上がった。だが、その計画は事前に察知され、グループのメンバー二人が虐殺されてしまう。虐殺の首謀者は巨大組織“マザー・カンパニイ”。一人生き残ったハンナは、からくもその惨劇の場から脱出し、バスク地方に隠遁する孤高の男に助けを求めた―“シブミ”を会得した暗殺者ニコライ・ヘルに。世界中を熱狂させた冒険小説の金字塔。
著者等紹介
トレヴェニアン[トレヴェニアン][Trevanian]
覆面作家。1972年に冒険小説『アイガー・サンクション』を発表し、高い評価を得る。その後『夢果つる街』(1976)、本書(1979)、『バスク、真夏の死』(1983)などを発表、世界中の読者を熱狂させた。2005年12月14日に死去。本名がロドニイ・ウィリアム・ウィテカーであることがわかっている
菊池光[キクチミツ]
英米文学翻訳家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
absinthe
172
孤高の暗殺者の活躍を描いた小説のはずだが、上巻は生い立ちに焦点が絞られる。主人公はまだ動き出してすらおらず、体のいいお膳立てなのだが、そのお膳立てがとにかく面白いのだ。シブミは惻隠の情のような言葉にしがたい至高の思想とある。日本人に育てられ日本の思考を体現する。日本のシブミを体得した暗殺者という設定だけ読むと、何やら日本大誤解小説のようにも見えてしまうが、深い調査の上に書かれたものだと納得できる。時代は日米戦争前から敗戦の混乱期まで。文化の比較において、日本に好意的。むしろ米国側を幼稚と指摘。2021/12/20
NAO
74
国際的にも名の知れた暗殺者ニコライ・ヘル。上海で育った亡命ロシア貴族の末裔がどうしてそれほどの技量を身につけたのか。上巻の大半が、ニコライの背景の説明に費やされている。「シブミ」という西洋人とはかなり異なる考え方、独特の技量の説明は、確かに西洋人にとっては興味深いのだろうが、ちょっと長すぎるのでは。とにかく、下巻へ。2020/02/04
財布にジャック
67
少し前ですが、本屋で平積みされていた「サトリ」という小説に興味を持ちました。「シブミ」の前日譚をドン・ウィンズロウが書いたものということなので、まずはこの「シブミ」から読むことにしました。導入部の序盤100ページ近くまでは退屈でしたが、その後は夢中になりました。ヘルがどうししてスパイになったのか、その半生が描かれます。日本が舞台になり、日本人も沢山登場します。アメリカ人の作者が、違和感なくこんな風に日本を捉えてくれたことを嬉しく思います。シブミの題名も光っています。2012/02/28
ntahima
56
『アイガー・サンクション』『夢果つる街』読了済。著者の情感溢れる筆致は大いに認めるものの、欧米作家の描く日本という設定に違和感を覚え、今日まで読まずにきた。話の本筋よりは、ゴルゴ13を思わす稀代の暗殺者の出生の秘密と戦時下の上海・日本での青春時代の描写が秀逸。アメリカ人とは思えない日本文化への理解と共感。もし日本学の泰斗ドナルド・キーン博士が謀略小説を書けばこの様なものになるかも。現代日本人には決して書けない廃れゆく日本の美への哀惜の念。日本人の目には心地良いが肝心の母国の読者が理解できたのかが気になる。2012/04/17
Panzer Leader
44
「第89回海外作品読書会」孤高の暗殺者ニコライ・ヘルを巡る冒険・スパイ小説との認識で読み始めたが、まず驚くのは戦中戦後の日本で育った情景・文化が日本人以上に瑞々しく描かれている事。中でも育ての親ともいえる岸川将軍、大竹七段達との交流・会話に魅せられる。本人がまだ回想場面でしか登場しない上、暗殺者としての成果もサラッと語られるのみで、いくらでもその話を発展させていけそうで、だからこそウィンズロウも続編を書けたのだと思う。CIAをも傘下におくマザー・カンパニーとどんな対決が待っているのか、期待を胸に下巻へ。2017/06/25
-
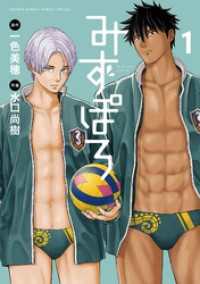
- 電子書籍
- みずぽろ(1) 少年サンデーコミックス…
-
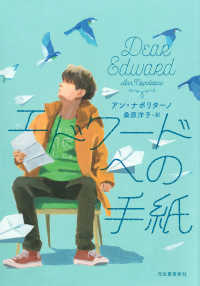
- 和書
- エドワードへの手紙