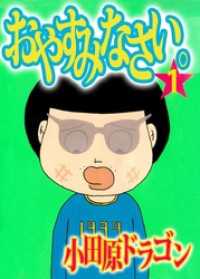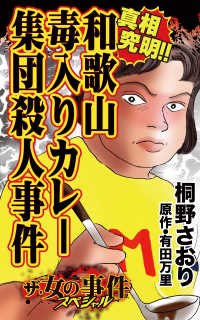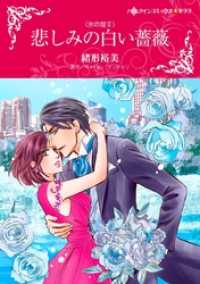出版社内容情報
文化人類学、SF、バーチャルアイドル――《信仰》をテーマに繋がる柴田勝家の真骨頂。「クランツマンの秘仏」ほか全6篇の短篇集
内容説明
人が死後に自らのライフログから分身を遺せるようになった未来、“この世”を卒業するバーチャルアイドルのラストライブを舞台裏から描く書下ろし表題作のほか、コロナ禍によりウェブに移行した神事がVR空間上の超巨大競技へ進化していく「オンライン福男」、“信仰が質量を持つ”ことの証明に全生涯を捧げた東洋美術学者をめぐる異常論文「クランツマンの秘仏」など、文化人類学と奇想が響き合う傑作集。
著者等紹介
柴田勝家[シバタカツイエ]
SF作家。1987年東京生まれ。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻博士課程前期修了。2014年、『ニルヤの島』で第2回ハヤカワSFコンテストの大賞を受賞し、デビュー。2018年、「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」で第49回星雲賞日本短編部門受賞。2021年、「アメリカン・ブッダ」で第52回星雲賞日本短編部門を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こら
85
地球滅亡後の文京区で暮らす宇宙人のゆるゆるライフ、火星での宗教の伝播を考察する論文等々、そのテーマの引き出しが多彩かつその組み合わせが絶妙で、6編のまさに「奇想」の妙味が味わえます。ポストコロナSF「オンライン福男」は現実のコロナ情勢からメタバースへと広がる壮大さ。信仰が質量を持つ事を証明しようとした学者の伝記「クランツマンの秘仏」。備考が最後の一撃風になってるのが心憎い。そしてベストは、往年のバーチャルアイドルのまさにラストライブを描いた表題作。アイデアの奇想もそうですが、登場人物達の内面描写もお美事!2023/04/27
アナーキー靴下
66
『アメリカン・ブッダ』が大変面白かった著者による短編集が去年出ていたことを知り読む。一番好きなのは「オンライン福男」、コロナ禍✕メタバースという現在と地続き感ある内容。論文風の「火星環境下における宗教性原虫の適応と分布」も良かった(わからないところも多々あったが)。でも同じく論文風の「クランツマンの秘仏」は乗れず、こちらは奇譚っぽくしてくれてたら好みだったかも。「絶滅の作法」は緩さが良い。「姫日記」は…長い、3行で、って気持ちに。表題作は上手いけど泣かせポイントがない方が良かった。もちろん泣いたけれど。2023/04/13
塩崎ツトム
56
収録作の多くはその他アンソロに収録されているので表題作について。自己を死後AIにする前例だとイーガンの「ゼンデギ」を思い出すけど、あれも学習の過程で個人の実存、つまり心の傷に触れる物語だった。現世に残すのはVtuberとしてのわたしか、それともだれかの父親・母親としての自分か。平野啓一郎の分人ともつながる話なのかもしれない。「わたし!」の意識=魂は、他者とのはざまにあるのかもしれない。小松左京の「虚無回廊」に人工実存というのがあったが、人工知能と人工実存、違いなんてないのかもしれない。2022/12/13
さっちゃん
54
SF風味の6話収録の短編集。どんどん過熱していく「オンライン福男」、こんな未来は来てほしくない「絶滅の作法」、クソゲープレイ日記にニヤリとする「姫日記」、死後に分身を遺せるようになり死んだバーチャルアイドルのラストライブを開催する「走馬灯のセトリは考えておいて」が好みで楽しめた。特に表題作が好き。推しが死後もライブや配信をしてくれて、自分が死んでからも推し活ができる。これ全オタクの悲願では。実用化したら世の中混乱しそうだけど、大切な人が死後も側にいてくれるなんてちょっと実現してほしい気もする。2024/02/28
オフィーリア
48
これは優勝です。魂と信仰をベースとした6作のSF短編集。奇想を圧倒的なディテールで補完して論文的に仕上げた異常論文達に唸らされたり、「姫日記」に爆笑させられた後に、最高にキャッチーで圧倒的な完成度の表題作に感動させられる。オススメは全部です。2025/07/04