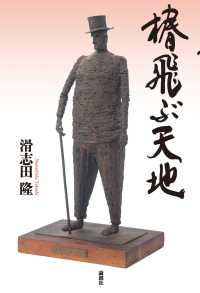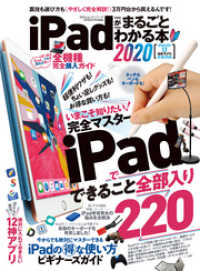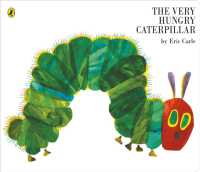内容説明
現代日本SF誕生から60周年を記念して、第一世代作家6人の傑作選を日下三蔵の編集により刊行するシリーズ。第2弾は、日本SFの巨大なる父、小松左京。デビュー短篇にして直木賞候補作「地には平和を」、小松自身が最も好きな自作と語る中篇「神への長い道」、そして半世紀前にネットワーク社会の弱点を予見した長篇『継ぐのは誰か?』ほか、人類進化を生涯のテーマとした小松SF傑作中の傑作8篇を収録。
著者等紹介
小松左京[コマツサキョウ]
1931年、大阪府生まれ。本名・実。京都大学文学部卒。62年、投稿短篇「易仙逃里記」が“SFマガジン”に掲載されてデビュー。たちまち同誌の常連執筆者となる。63年、第一短篇集『地には平和を』を刊行。64年、第一長篇『日本アパッチ族』、第二長篇『復活の日』を相次いで刊行。70年、大阪万博に委員として参加。同年、国際SFシンポジウムの実行委員長も務める。73年、『日本沈没』がベストセラーとなり、同作で翌年の第27回日本推理作家協会賞を受賞。80年から日本SF作家クラブの第三代会長を務める。85年、『首都消失』で第6回日本SF大賞を受賞。2000年、小松左京賞を創設。2011年7月、没
日下三蔵[クサカサンゾウ]
ミステリ・SF評論家、フリー編集者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yamatoshiuruhashi
49
昭和30年代後半から40年代に描かれた作品を8作。戦争体験、膨大な科学的知識、哲学的思索の上に築かれた世界。まさに小松左京は知の巨人である。神と人の関わりは何か?人とは何なのか。そこに最新の科学とフィクションが織り込まれる。「神への長い道」と「継ぐのは誰か?」は嘗て単独で出版されたものを高校時代に読んでいる。余りに深い内容だったのでその時には十分咀嚼できていなかったと今回読んでみて改めて知った。これだけの重量感溢れる作品を理解するには、自己の存在をしっかりと考えることや人生経験が必要だったということか。2022/01/29
ヨーイチ
45
700頁あまりの分厚さの半分くらいを「星を継ぐもの」が占める。全般に「SFを読んだなぁ」って感慨があった。この場合の「SF」は中学生くらいからボチボチ読み出した、今よりももっと間口が狭かった時代の感覚を含んでいて、科学とか知識にもっと夢が乗っかっていた時代。手塚治虫に通じるかも知れない。これも感覚だが「アニメ臭」「キャラクター臭」が当時は無かったって気がする。筒井康隆だったと思うが、小松左京を称して「小松左京は膨大な知識、資料を項目毎にノートではなく行李で保存してある」って言っていたのを思い出した。2018/03/12
geshi
35
なぜ小松左京が「知の巨人」と呼ばれたのかの一端がうかがい知れるチョイスの傑作選。人類の知性に対する疑念や諦観が色濃い作品が多かった。『地には平和を』は戦中記としての描写がとても上手いからSFへのジャンプと「いま」の不確かさが活きる。『神への長い道』は長編でも十分通用するアイデア。諦観の先にあるものを予感させる。『継ぐのは誰か?』は青春小説・ミステリ・秘境冒険とジャンルを次々と飛び越えてストーリーのまとまりを欠いてさえいても、やりたいことを詰め込んでいる熱量を感じる。2018/01/06
ぜんこう
32
2017年の最後は700頁余りのこの本。「地には平和を」「時の顔」「紙か髪か」「御先祖様万歳」「お召し」「物体O」「神への長い道」そして文庫本の中に長編の「継ぐのは誰か?」 全て既読かと思ってたら「継ぐのは誰か?」は未読でした。 いろんな小松左京さんを楽しめた太い一冊です。「継ぐのは誰か」は人類進化に関する重いテーマだけど読むのがやめられませんでした。2017/12/31
楽
30
17年電子版。60年代の作品から日下三蔵が編集。「三体」の劉慈欣『超新星紀元』の訳者あとがきに「お召し」が取り上げられていたので購入。「神への長い道」などは「三体3」の未来の地球を思わせる。長篇「継ぐのは誰か?」もだが、技術が進歩する一方、精神的な行き詰まりに直面する人類が描かれる。膨大な知識に裏打ちされた重厚な数字、科学的な話から、深刻な状況に置かれた人間の本質的な姿、あるいは俗な話に持っていくのはさすが。2025/08/28