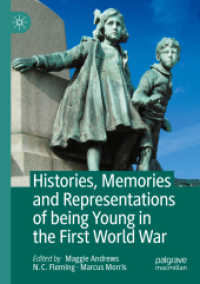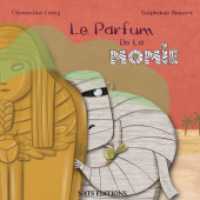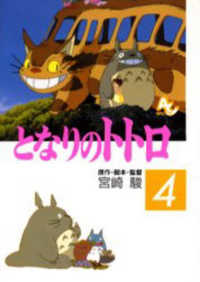出版社内容情報
人生のすべてを記録・再生できる技術により“死後”の概念が失われた未来。南洋諸島で学者ノヴァクは死出の舟を造る老人と出会う
柴田 勝家[シバタ カツイエ]
内容説明
人生のすべてを記録し再生できる生体受像の発明により、死後の世界という概念が否定された未来。ミクロネシア経済連合体を訪れた文化人類学者イリアス・ノヴァクは、浜辺で死出の船を作る老人と出会う。この南洋に残る“世界最後の宗教”によれば、人は死ぬと“ニルヤの島”へ行くという―生と死の相克の果てにノヴァクが知る、人類の魂を導く実験とは?新鋭が圧倒的な筆致で叙述する、第2回SFコンテスト大賞受賞作。
著者等紹介
柴田勝家[シバタカツイエ]
1987年東京都生まれ。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻所属。外来の民間信仰の伝播と信仰の変容を研究している。『ニルヤの島』が第2回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作となり、ハヤカワSFシリーズJコレクションより単行本化されデビュー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
43
【始原へ15】文化人類学SFと聞き、ハードSF好きとしては読み逃すわけにはいかない。舞台は、マリノフスキーなど民族誌の宝庫のメラネシア。日系文化人類学者が、この地ですでに失われた信仰の調査に入る。いかにも文化人類学的な雰囲気が漂うが、これはSF。物語が進むにつれて、このメラニシアの<現在>は、DNAコンピューターにより統治された世界であることが、徐々に明らかになってくる。死後の世界はあるのかという宗教の<始原>が、科学技術の<進化の果て>の姿に重なってくるという逆説。文章が荒っぽく、複数のプロットが↓2021/04/15
ソラ
34
文庫版を機に再読。初見の時はわからなかったことも何となくわかってきたかな。断片がちりばめられているため最初はなんだかよくわからないところではあるけれど結末に近づくにしたがって収斂していくところが見事。2016/12/10
泰然
18
第2回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作。人生のすべてを記録し再生できる生体受像の発明により、死後の世界という概念が否定された未来が訪れたとしたら?かつて日本が国際連盟によって委任統治を託された南洋諸島・ミクロネシアを舞台にハードSFと民俗学が融合した独特さと不規則ストーリーが読者を引き付ける。 折口信夫は、紀伊半島から海のかなたへ目をやったとき海の先に命のふるさとがあるという感慨を持ったとされるが、本書は思考実験としてそんな日本人的死生観や、人間が物事を物語で考え拡散する存在として南洋に死の島を浮かべる。2019/12/15
おくりゆう
18
以前もありましたが、小島秀夫さんの帯に弱いみたいです(笑)断片的な物語がやがて統合されるのですが、解説を読んで理解が出来る部分もあって、個人的には難解でした。それでも読み進めたくなる吸引力は凄く、読み直したい作品です。2016/09/21
hide
17
人生は物語だ。物語性を欠いた時、人は模倣することで自己を補強しようとする。今が過去になり未来が今になるような記憶の断片化が、連続しない記憶が世界から切り離されると怯えたからこそ、人は死後の世界を創り出した。DNA以外の方法で人から人へ継承される情報__人生の物語であるミームが急激に成長し、死後の世界が消滅した未来。DNAと同じように人を乗り物にして複製を繰り返す存在。そんな存在を何と呼ぼう。では人とは何か?怒涛のラストにその答えはあるのかもしれない。2024/04/28