内容説明
この世界のどこかにオルシニアという名の国がある。12世紀のなかば、“オドネ”という邪神を信仰する野蛮な異教徒からこの国を守り、神の教会の忠実な守護者として敬愛されるフレイガ伯爵の城館で起こったある真冬の夜の出来事をはじめ、17世紀、オルシニアの王位継承をめぐる内乱に巻きこまれたモーゲの姫君の数奇な一生、そして1962年、田舎で一週間の休暇を過ごそうとした青年の恋の物語など、SF界の女王ル・グィンが、自らの想像の王国オルシニアを舞台に、そこに生きる様々な時代の、様々な人々の姿を通して、愛とは、自由とは何かを見事に謳い上げた傑作短篇集!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Die-Go
47
図書館本。追悼ル=グウィン。世界のどこかにある(恐らく東欧)架空の国、オルシニア国を舞台に人々の静謐な生活が物語られる短編集。架空とは言ってもファンタジー的な要素はなく、むしろ淡々とした筆致で描かれているため、その抑揚の無さにちょっと苦心した。でも、それぞれの物語に美しさがある。★★★☆☆2018/01/31
波璃子
20
東欧のどこかにあるというオルシニアという国が舞台。各短編の終わりに年代がはっきりと書いてあるという面白い試みがなされていて、それによってこの国が本当に世界のどこかにあるんじゃないかという気分にさせている。1150年が舞台の「塚」や1640年が舞台の「モーゲの姫君」といった昔の作品もいいし、盲目の青年との恋を描いた「夜の会話」も好み。静かな空気からしっかりと語りかけてくるものがあります。2015/05/15
tom
19
グウィンは、SFを書く人だと思っていたのだけど、この本は東欧に設定された架空の国の年代史。そこで暮らす人を映し出しながら、グウィン自身の価値観を語る。好きだったのは「音楽によせて」かな。貧乏だけど、仕事の合間に作曲をする男がいた。彼は、書いた曲を持って、音楽マネージャーのところに行く。マネージャーは声楽曲を美しいと褒める。もっと書けという。演奏会で取り上げると言う。でも、彼が書きたいのはミサ曲。これを書きたいと訴えるが、マネージャーを説得できない。望みかなわず帰途に就く。しみじみといい感じの短編です。2021/08/22
roughfractus02
14
なぜfactとfictionの語源がラテン語fecere(作る)なのか?地球上にありながら実際にはない「オルシニア国」という本書の設定から、この問いに対する作者の回答を想像できそうだ。確かに、実体という意味ではこの国は想像の中にしか存在しない。が、事実に権力関係を見出す人類学者からすれば、権威が与える情報で作られた事実も個人の想像とそう変わらない。1150〜1962年までのオルシニア国に関する11の短編を収録した本書は、虚構はそんな事実に距離を置く作法である、と読者と登場人物を突き放す三人称の語りで示す。2024/01/04
ペイトン
14
「闇の左手」を読んだ直後に読んだせいか,入って行けずどうしよう?短編集だから気に入ったタイトルから読もうかと思いながらも順番に読みました。「イーレの森」「夜の会話」が良かったです。2015/09/06
-
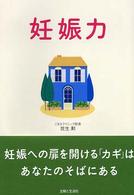
- 和書
- 妊娠力








