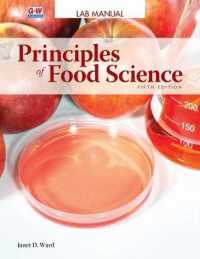出版社内容情報
私たちは、あの名著を「誤読」していた。
『古事記』『論語』『おくのほそ道』『中庸』──代表的4古典に書かれている「本当のこと」とは? 私たちは何を知っていて何を知らないのか。古典の「要点」さえ理解できれば自分だけの生きる「道」が見えてくる。自分なりの価値観を見出していくために。古今東西の名著に精通する能楽師による、常識をくつがえす古典講義!
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
neimu
69
安田さんの本は以前何冊か読んだことがあるなあと思いながらパラ見。その時のインパクトが強かったので、この本はまるで水のようにサラサラ過ぎて、心に残る所が少なかった。本当に基本過ぎて、もう少し深く語ってくれてもいいんじゃないかと欲求不満。でも、古典ってハードル高いなあと悩んでいる人には、このぐらいがいいのかもしれないと思って出されたシリーズなんだろうね。選ぶ本を間違えたというか、まあ、役に立つというからどんな内容かなと思って手に取ったんだけれど、もともと古典が好きで興味ある人にはそれほど必要ない本かも。2020/02/22
モリー
68
学生時代、古文・漢文の試験に苦しめられた身としては、古典と聞くのも嫌でした。しかし、あこがれの読み友さんに近づきたくて、古典に親しもうと思い立った矢先に出会ったのがこの本。「役に立つ」という文句にも引っ掛かりました。このタイトルに、打算的な私の財布の紐がゆるみました。しかし、読み終わる頃、こう思いました。古典が私の人生の役に立たなくても構わない。これ程面白いものを読まずには死ねないと。四十歳を不惑ともいいますが、孔子の時代に「惑」の文字は無かった!?では、本当はどんな意味だったのか、知りたくはないですか?2020/01/21
おさむ
37
さまざまな古典には誤読や誤解があると指摘する本著。驚きだったのは、論語にある「40にして惑わず」の意味が「人生に迷いがなくなる」ではなく「自分を区切らずにさまざまなことにチャレンジすべき」とする解釈です。自分が40歳になった時、迷いだらけで全然駄目だと思った記憶がありますが、こう考えた方が腑に落ちます。また「己に如かざる者を友とすることなかれ」も長年変な言葉だと思ってましたが、「自分と一体化(共感)できない人を友にしてはいけない」という意味ならしっくりきますね。ツマのオススメ本でした。2020/05/13
Sakie
29
古典は単に古い書物というだけでなく、何か問題を乗り越えるために人々によって繰り返し揉まれ残ってきたもの。ただし国や時代が違えば常識や精神性が違うのは当然で、求めるものが違えば解釈が違っていくのも考えてみれば当然なのである。文章を改めて読み解きながら、滑らかに推論していく安田先生の思考のしなやかさ、なかでも孔子とHuman2.0を同軸で語るダイナミックさにはしびれる。かっこいい。安田先生の考えに触れる入門としてお勧め。「四十而不惑」を『四十にして区切らず』とする解釈が好きだ。四十だから、敢えてやってみよう。2020/02/05
しょうじ@創作「熾火」執筆中。
27
【1回目】『古事記』『論語』『おくのほそ道』『中庸』について、漢字の使われ方や語義の変遷などを手がかりにして、その現代的な意義を掘り起こそうとする試みである。言葉は、いわば「生き物」なので長い年月の間に意図せざる変容をすることがあることを追いかける。例えば終結としての「死」という観念がなかったことや、「四十にして惑わず」が、区別や限界を設けないという意味があったことを明かす。古典の「新しさ」の発見が、見事に展開されている。2020/01/31