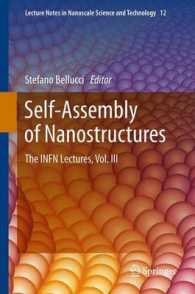出版社内容情報
「自然を愛する」とは、こういうこと
動物の言葉を使いこなし、個性豊かなたくさんの動物たちと暮らす博物学者・ドリトル先生。助手のスタビンズ少年とともに、その独特な能力と知性とユーモアで愉快な旅を繰り広げる物語は、多くの子どもたちを魅了し、長く読み継がれてきた。今回は、子どもの頃にドリトル先生の物語を読んだことがきっかけで生物学者を志したという福岡伸一氏を講師に迎え、シリーズの最高傑作『ドリトル先生航海記』を新たな視点で読みとく。奇想天外で痛快な冒険物語の旅を楽しみながら、自然や動物との関わり方、「公正」であることの意味、豊かな創造力の源となる「好奇心」の大切さなど、現代にも通じる知恵や生き方のヒントを学んでいく。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
れみ
33
NHK-Eテレ「100分de名著」2024年10月のテキスト。動物と話すことができるドリトル先生が冒険するお話を楽しみつつ、自然とのかかわり方とか色々なことを考えさせてくれる時間になった。ドリトル先生が動物を大切にしながらもお肉も食べるところが印象的だった。今の時代では「動物の命大事→肉食べるなんてとんでもない」みたいな極端と言うか0か100かみたいなことになりがちな気がしていて、でも人間が生きていくのって何かしら矛盾に満ちつつも自分にとっての「芯」が必要なんだなとあらためて思ったりした。2024/10/28
ひまわり
26
こどもの頃、夢中になって何度も読んだドリトル先生。先生が誰にでも敬意をもってお話すること、それ自体がたいしたことだったことだったのだ、あの時代。今になってわかるドクターの意味。先生は風変りなお医者さんだと思っていたが、ナチュラリストだったのか。ところどころ実在の人物を紛らわせていたとは。大人になった今、読み返してみたいシリーズとなった。2025/01/10
joyjoy
18
積読棚にある福岡訳の「航海記」。この機に読もうと、先にこちらを。ドリトル先生のフェアネスに注目してシリーズを読み直したくなる。「グッド・ノーティサー」。何にでもよく気づくようになる、ということは、「ヨクミル・ヨクキク・ヨクスル」につながるなぁと、嬉しくなる。初めて目にした「ピュシス」という語。ロゴスとピュシスの話もとても興味深く読んだ。「ドリトル先生が大事にしているのは、好ましいかどうか、美しいかどうか…」。「美」ときた! 先日ラジオで聞いて気になった柳宗悦「雑器の美」も読んでみなくては。つながっていく。2024/10/01
どりーむとら 本を読むことでよりよく生きたい
15
動物の言葉が分かるようになるためには、動物のことをよく観察することだという言葉が心に残りました。その言葉を知っただけでも、この本を読んでよかったと思いました。動物だけではなく、植物や人間でもその相手をよく見ることによってより深く会話ができると感じました。「これはこのようなものだ」と自分がおもってしまいます。そこで思考が停滞してしまいます、よりよく観察していこうと改めて感じました。フェアネスであるというのはどういう姿勢で人や物に接することかという事を教えてくれた本でした。2024/10/13
北風
14
今年のブックサンタは、ドリトル先生航海記にしました。しかし、毎度のことですが、ここまでドリトル先生を掘り下げる!? 考えすぎじゃないかと思うほど愛が深い。ナチュラリスト、ロゴスとピュシス。どの細胞がなにになるのか、最初から決められていない。相互作用でなにになるのか決まっていく。社会の仕組みもそういうものじゃないかしら? 二次創作までしてるなんて、興味はある。続巻も読みたいとは思っているんだけど、岩波はちょっと訳がとっつきにくい気がするんだよな。2024/12/22
-
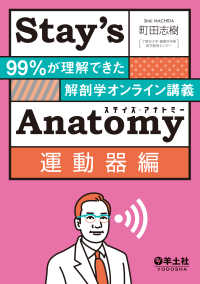
- 電子書籍
- Stay’s Anatomy運動器編 …