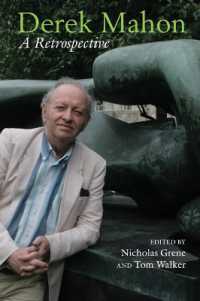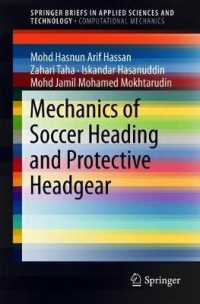出版社内容情報
「新約聖書」の4つの「福音書」に描かれた、弱きもの・小さきものに寄り添ったイエス・キリストの存在は、現代人にどのような意味を持つのか。信仰者に留まらない開かれた書物として、また「理解する」ものではなく、各々の人生に照らして「感じる」ものとして、キリスト教の聖典を読み直す。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kei-zu
15
新約聖書のうち福音書の概要をコンパクトにまとめる。単純な「イエスの生涯」の解説ではなく、「書かれていることから、どのように読み解くか」。本書で著書が師と紹介がする井上洋治神父のミサは、私も何度か授からせていただいたことがあり、神父のやさしい口調が思い出されました。2024/09/08
石橋陽子
13
読む終えることが出来ない、読み終えたなんてとても言えない、そう感じる本と出会うことは読書の醍醐味である。多く読むのではなく深く読む本。これが『福音書』だと思う。こちらは指南書であるが、新約聖書をゆっくりと読み、自分の中で解釈する時間を持ちたいと思った。イエスの教えで重要なのは、互いに愛し合うこと。他者だけでなく、自分自身も愛すること。自分に弱さや至らなさを胸に読む時、あなたのままでよいという深い慰めと安堵のコトバに出会えるという。2024/10/01
ラウリスタ~
9
このシリーズの中ではあまり勉強にならない。学術的ではなく一信仰者としての新約聖書の読み方で、それもとても普通な読み方なので、全く聖書を開いたことがない人以外にとっては参考になることはあまりない(そういう人がターゲットなのだと思う)。例えば15ページに福音書が四つあるとした上でその理由は明確ではないと片付けてあるが、ここで読者が知りたいことはその四つの制作年代の順番とどれがどれに影響を与えたのか(例えばルカが一番詳しい理由はなど)だろう。また23頁に「イエスの父であるヨセフ」という記述があるがこれはアウトだ2025/05/18
Michio Arai
5
著書の若松英輔さんの本は初めてではない。やや苦手である。やはり、今回も改めて感じたことだが貝汁の身に砂が残っている時のガリッとした舌触りに似た読後感である。イエスキリストやキリスト教の教えを説明する時に分かりやすくと腐心しているのは理解するが、例えが安直すぎるように感じる。その違和感の手がかりが今回読むにあたって偶然だが、若松の師がインカルキュレーションを多用する人であることを知り、謎が解けた。言の葉は言霊であり「読書百篇意自ずから通ず」ということもある。あくまでも身近な例えに走らず原典に忠実でありたい。2024/08/31
乱読家 護る会支持!
3
僕がクリスチャンをやめた理由は、知らず知らずのうちに神と取引をしていたから。神と取引をしている以上、僕の成長は無いと気づきました。教会を離れましたが、信仰を捨てたわけではありません。 そして「誰かをゆるすことは、自分がゆるされること」の言葉が響きました。僕は「ある人」を心の底から、ゆるせてはいません。「相手が僕を許せば、僕もゆるす」と取引を考えていたのかもしれません。残りの人生、その人をゆるすためには、どのような心の持ちようであればいいのか?自分の内面の問題として、自分と向き合っていきたいと思いました。2025/03/31