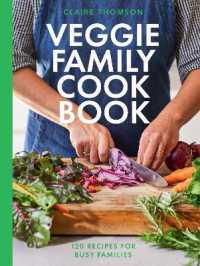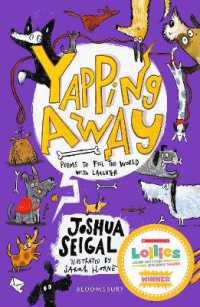出版社内容情報
「人はいかに生きるべきか」を徹底的に考え抜き、2000年以上も生き残った古典中の古典。人生の目的はなんだろうか? 幸福はいかに獲得しうるのか? 古代ギリシア最高の知性による思索を、平明かつ本格的に解きほぐす。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ともふく
12
Eテレの番宣で興味を持ち読んでみた。古代ギリシャの哲学者の考えが、現代においても全く古くなく、共感できる。人間の本質を捉えているのだと思う。アリストテレスについて他の本も読んでみようと思う。2024/02/12
乱読家 護る会支持!
7
NHK100分de名著のテキスト。有名な哲学書を取り上げてくれることが多い番組ですが、難解な哲学書を噛み砕いてわかりやすく説明してくれます。 アリストテレスの倫理学をざっくり言うと、『人の行動は「幸福」を目指している』ということなのですが、人生を目的主義的、達成主義的に捉えているわけではなく、むしろ善き行いを繰り返すプロセスによって善き人格を目指すといったプロセス主義的な哲学のように思います。 僕自身も、結果よりはプロセスを楽しみたい人間なので、アリストテレスの本は読みやすくわかりやすいなぁと感じました。2024/02/02
みのくま
7
古典を現代的な感性で「役立つ」かどうかは議論の余地があろうと思う。著者は「役立つ」派であり、それは一定の説得力がある。アリストテレスの思想は中世に再発見されてから近代哲学まで厳然たる影響力を有し、それは現代哲学の基底を為している。現代社会の根底に彼の思想の一端がインストールされているのならば「役立つ」のも当然であろう。しかし他方で、アリストテレスは中世にトマス・アクィナスによって再発見されている事に注意すべきだと思う。この受容の経緯は、果たしてアリストテレスの「本当」の思想を汲み取れていたのか疑問なのだ。2023/12/19
うえ
6
徳と技術の類似性を説く倫理学書の解説。悪徳は、繰り返して身に憑いてしまうように、徳も繰り返して身につくという。そして徳を身につけるには善き共同体(の中にいる師匠や模範)というモデルが必要。そして徳を身につけた者が今度は共同体を支えるという。ここがコミュニタリアンへと繋がるのかなと。「『ニコマコス倫理学』は、徳に基づく社会的生活において、どのように幸福を実現するかという話がほとんどを占めています。そして最後、ほんの20ページほどで、究極的な幸福は観想的活動によってこそ得られるという話が本格的に出てきます」2025/05/31
らる
6
いかに良く生きるかを考える=倫理学。史上初の体系的な林学の本/目的には階層がある。最高の善は「幸福」である/エトス=習慣は、エートス=性格・人柄を形成する/「幸福」は遠い未来にあるのでなく、「いま、ここ」の行為に常に意味を与え続ける/善の3種類⇒快楽的、有用的、道徳的/3種の生活類型⇒快楽的、社会的、観想的(知ることに喜びを見出す)/枢要徳=賢慮、有機、節制、正義/徳を身に着けるのは、技術を身に着けるのと同じ。モデルが必要。行動が必要/中庸は、まあまあ…ではなく、「ど真ん中」を射抜くこと2024/01/27
-

- DVD
- Mr.ビーン Vol.2