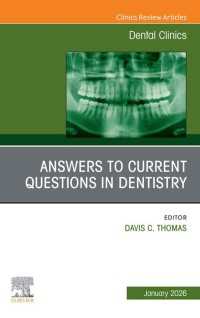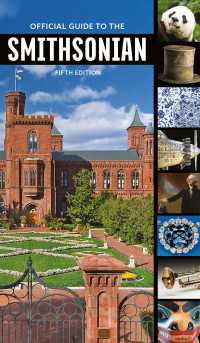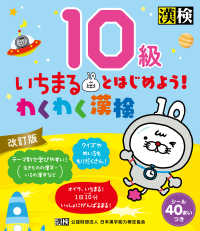出版社内容情報
現代の出発点は1920年代にあった
東京都知事選や米大統領選など、政党の存在意義がわからなくなるようなケースが増えてきた。一方、政党支持率が落ちても政党の存在を前提とした政治システム自体はびくともしない。なぜか? その理由を、ちょうど100年前のデモクラシー成立の経緯に焦点を当てて説くのが本書である。1924年の加藤高明内閣に「政党政治の確立」を見て、そこに至る過程で「民主政=政党政治」が渇望されていたこと、1932年の5・15事件以後も「政党政治への復帰」が目指されたこと、戦後の「民主化」が言わばその復活強化であったことを明らかにし、「戦前日本=軍国主義」というイメージを吹き飛ばす。「目から鱗」の日本近代史!
(仮)
序 政党政治のアーキテクチャ:第一次世界大戦後の政治改革
一章 立憲政治の中に育まれる民主政治:日本の民主化と第一次憲政擁護運動
二章 原内閣と憲政会の苦節十年:政党内閣制の準備 1918-24年
三章 護憲三派内閣の矜恃と男子普通選挙制の実現:政党内閣制の成立 1924-27年
四章 大政党内閣とマルチ制度ミックスの変容:政党内閣制の展開 1927-32年
五章 危機の時代の非常時暫定内閣:政党内閣制の崩壊 1932-36年
六章 政党政治家の苦節十年と占領下の再建
結 自由と多様性の基盤を育む:近代日本の民主政治と現在
内容説明
民主主義は米国のプレゼントではない 「日本の軍部が台頭したのは政党が腐敗していたから」とか、「大正デモクラシーが戦前民主主義のピーク」というイメージは歴史の事実と一致するのか。否、むしろ近年明らかになったのは、政党政治に肯定的な元老や、婦人参政権を推進する政党であり、協調外交維持に努める政府、軍縮に協力的な軍部大臣である。本書は、議会多数党間で政権交代を行う現代的な仕組みが「憲政常道」の名で百年前に形づくられていく様子を明らかにし、日本の民主主義の出発点が第一次世界大戦後にあったと見る。多彩な引用と篤実な叙述で蘇る、忘れられた戦前日本の姿!
目次
本書に関連する主な政党の変遷
序章 第一次世界大戦後の世界と日本―政党政治の智慧と経験をめぐって
第一章 二つの政友会内閣と大戦後の国際協調外交―転換期の帝国日本と初の政党内閣期 一九一八‐二二年
第二章 転換期の首相選定と第二次憲政擁護運動―政党内閣制の確立を求めて 一九二二‐二四年
第三章 二つの加藤高明内閣と政党内閣制の成立―男子普選体制下での三党鼎立 一九二四‐二七年
第四章 昭和天皇と「憲政常道」下の二大政党内閣―政友会と民政党の強さと脆さ 一九二七‐三一年
第五章 五・一五事件と政党内閣制の中断―世界大恐慌下での弱者の反動 一九三一‐三二年
第六章 二・二六事件と政党内閣制の崩壊―非常時暫定政権と溶けゆく「常道」 一九三二‐三六年
結論 自由と多様性の基盤としての民主政治を日々運営する
著者等紹介
村井良太[ムライリョウタ]
駒澤大学教授。1972年生まれ。神戸大学大学院法学研究科博士課程修了。博士(政治学)。著書に『政党内閣制の成立一九一八~二七年』(サントリー学芸賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Tomoichi
MUNEKAZ
雷電爲右エ門
takao