出版社内容情報
西欧中心のローマ史観を根底からくつがえす
「ローマ史は五賢帝時代がピークで、あとは下降線」。世界史を学んだ人が抱くこんなイメージは、18世紀イギリスの歴史家エドワード・ギボンが印象的に描き出したもので、日本にも広く知れ渡っている。しかしそろそろこうした「西ヨーロッパ中心主義」を解体する時期ではないか――期待の俊英が、ローマが2000年続いたのは東側に機能的な首都・コンスタンティノープルを作ったからだとし、勅令や教会史に現れる「儀礼を中心とした諸都市の連合体」としてのローマ帝国像を生き生きと描き出す。コンスタンティヌス帝やユスティニアヌス帝ら「専制君主」とされる皇帝たちは、本当は何に心を砕いていたのか? 最新研究を踏まえた驚きの古代史!
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
45
古代末期、コンスタンティノープルがローマ帝国東方の首都になっていく過程を追った本。著者は気鋭のローマ史家。2020年刊。「3世紀の危機」に対処するため各方面に軍事司令官=皇帝が置かれたことで、地理的中心たるローマと政治的中心たる皇帝に徐々に分離が生じた。その後の歴史の中で東方ではコンスタンティノープルが皇帝の住まう都としての地位を得て「第2のローマ」になることができたが、分裂傾向の強かった西方世界の旧都ローマは再び政治的中心に返り咲くことはできなかったとする。東西分裂の過程を丁寧に追うことができる良書。2020/10/24
Nat
41
図書館本。世界史で学習した通りいっぺんのローマ帝国東西分裂ではなく、その過程がよくわかる内容だった。またずっと疑問だった西ローマ帝国の滅亡についても、何となく腑に落ちる記述を読み、そんな感じだったんだなぁと納得できた。コンスタンティノープルがいきなり首都になったわけではなく、徐々に発展していった様子もよくわかった。2023/11/19
鐵太郎
35
ローマ帝国史の見直しなのですが、目を付けたのがコンスタンティノープルがコンスタンティヌスによって「首都」として建てられた330年からユスティニアヌスが死ぬ565年までの200年ちょっと。この時代、ギボンなど近世の歴史学者が惰弱・無能と蔑視した東ローマ帝国と皇帝たち、帝国を腐らせたキリスト教などは、そんな非道いもんじゃないんだよ、だから西帝国が亡びてから(滅ぼしたのは東ローマといってますが)千年の長きにわたって東帝国が存続するいしずえが出来たんだよ、と。複雑で面倒ですが、こんなふう見直された歴史っていいね。2025/10/12
崩紫サロメ
29
東ローマ帝国の歴史を、ビザンツ帝国という長大なスパンではなく、あくまでも古代末期という枠組みで捉え直す。そこで鍵となるのが、「首都」コンスタンティノープルである。移動宮廷の弱みが首都の必要性を生み出し、皇帝が公司点ティノープルに定住するようになる。帝国西部がゲルマン人の侵攻を受ける中、東部は相対的な軍事的・経済的安定を背景に、元老院と市民団を備えた首都を持ち、帝国の中心へと移り変わる。「ローマはもう一つのローマによって滅ぼされた」という衝撃的とも言える結論も、納得のいく話であった。2020/11/10
ゲオルギオ・ハーン
25
コンスタンティノープルが帝都となるまでの経緯、関連して帝国末期の皇帝たちの政策意図や位置付けをポイントにして東ローマ帝国成立の意味を再考する意欲的な良書。コンスタンティノープルは成立と同時に帝国の中心になったわけではなく、コンスタンティヌス帝の時代はまだ肩書きばかりの街だった。それが次第に皇帝の支持基盤の本拠地として実務能力の高い騎士階級を官僚(名称的には元老院議員身分者として登録)として確保し、帝都ローマとも機動軍とも独立した人材プールを築きます。(続きます)2021/06/09
-
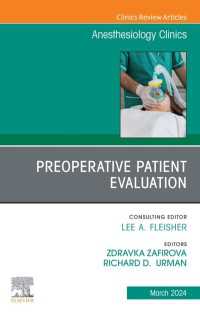
- 洋書電子書籍
- Preoperative Patien…








