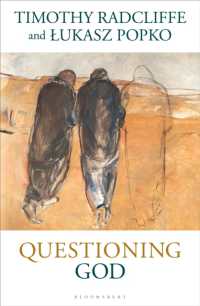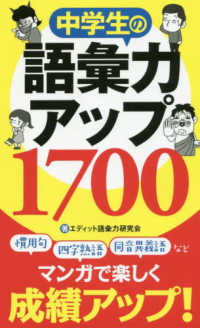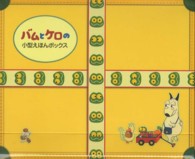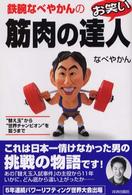内容説明
東日本大震災とそれに伴う原発事故を機に顕在化したITの諸問題。かつてない非常時に、政府、企業、マスメディア、そしてソーシャルメディアなど、各情報システムはどう機能したのか。それぞれの脆弱性および柔軟性を技術面から検証する一方で、鴨長明や寺田寅彦など過去の震災を伝えた古典なども取り上げ、「情報」が有する情緒表現の重要性を説く。安心・安全な社会を築くために、今後のITのあるべき姿とは?情報工学者であり歌人でもある著者が、システムと人心の両側面から、その方向性を提言する。
目次
序章 ライフラインとしてのIT
第1章 古典の伝える大震災
第2章 非常時のITはどう機能したのか
第3章 原発事故と情報開示
第4章 情報インフラの信頼性―みずほ銀行システムダウン
第5章 非常時のデマとフィッシング―情報セキュリティ
第6章 社会情報と個人情報―大きさと個別性
終章 幸福なIT社会の実現に向けて
著者等紹介
坂井修一[サカイシュウイチ]
1958年、愛媛県生まれ。東京大学大学院工学系研究科修了。工学博士。電子技術総合研究所(現産総研)、MIT、筑波大学などを経て、東京大学大学院情報理工学系研究科教授。専門はコンピュータシステムとその応用。また、歌人でもあり数々の賞を受賞、「NHK短歌」の選者も務める。主な著書に、『アメリカ』(若山牧水賞)、『ジャックの種子』(寺山修司短歌賞)、『望楼の春』(迢空賞)、歌書に『斎藤茂吉から塚本邦雄へ』(日本歌人クラブ評論賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
19
遊未
nchiba
ことよん
Shiho F