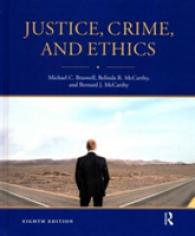内容説明
今日、すべての人が被害者意識を抱え、打ちひしがれている。現代日本を覆うこの無力感・閉塞感はどこから来たのか。石油危機に端を発する「七三年の転機」を越えて「超安定社会」というイメージが完成した七〇年代から、バブル景気を謳歌した八〇年代を経て、日本型新自由主義が本格化する九〇年代、二〇〇〇年代まで。政治・経済システムの世界的変動を踏まえながら、ねじれつつ進む日本社会の自画像と理想像の転変に迫る。社会学の若き俊英が描き出す渾身の現代史、登場。
目次
序章 左右の反近代主義のねじれ
第1章 「七三年の転機」とは何か―官僚制からグローバリゼーションへ
第2章 「超安定社会」の起源―高度成長・日本的経営・日本型福祉社会
第3章 多幸感の背後で進んだ変化―外圧・バブル・迷走
第4章 日本型新自由主義の展開―バブル崩壊後の日本社会
終章 閉塞感の先へ
著者等紹介
高原基彰[タカハラモトアキ]
1976年、神奈川県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。日本学術振興会特別研究員。聖公会大学校(韓国)訪問研究員をへて、現在、中国社会科学院訪問研究員。専攻は社会情報学、東アジア地域研究。日韓中の開発体制の変容とグローバル化にともなう社会変動を研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぷほは
3
刊行当初は中々理解できなかった奥行きを今回知ることができた。2009年刊行だがその後の趨勢を予言しているような箇所も多い。例えば女性→若者ときて最後の拠り所として「地方」が出てくるという論点など、その後の大阪における維新の登場などを想起するに背筋が凍る。うわ、この時の高原先生、いまの私よりも年下?勘弁してくれ……。2010年代以降、外国人を労働力(技能実習生)か消費者(インバウンド)としか見ることができず、コロナで右も左も上も下も内も外も閉塞感のある「いまの現代」、被害者意識だけで生きてる訳にもいかない。2022/01/23
msykst
3
核家族,会社主義,自民党の分配システムを前提にした「超安定社会」へのノスタルジーを語るのが右バージョンの反近代主義で,それは歴史的に超奇跡的な状況下において成り立っていたものなのでもう無理っしょ,と。で,左バージョンの反近代主義はその手の官僚的システムを批判している様に見えるけど,結局はまさにその分配制度への依存を前提にしているから社会制度として有効な対抗軸を作れず,バラバラに好き勝手な権利要求しただけだったんちゃうんか?と。ほんでいよいよそのシワ寄せも顕在化してきて残念な事になってるよね,と。 2009/08/31
Max Brown
2
自分自身が現代日本における「自由」と「安定」のジレンマに悩まされている人間なので、図書館で気になって手に取ったのだが、中々の良書だったので即購入を決意する。本書は一応社会学をベースにした現代史の本であるが、社会学において手薄になりがちな経済・経営的側面を大幅にフォローしつつ、1973年以降の「後期近代」の日本現代史を大局的ではあるが、非常に濃い密度で描き出すことに成功している稀有な書。主に経済に軸を置いた、日本の後期近代(的社会状況)を勉強・理解する上でかなり役立つ。これは何度か読み直さないと。2013/08/31
遠山太郎
2
必読レベルの傑作だと思った。社会言論は筆者の分析した<日本システム>、特に左右の反近代主義でとっても理解しがたくなってる。簡単な本ではないけれど、これだけの全体像がわかるものはそうない。優れた点は多数の視点を追っていること。経営者の歴史、学者の歴史、労働組合の歴史、政治の歴史・・・再読してきちんとまとめたい。2012/08/24
КИТАРУ МУРАКАМУ
2
政治的なポジションとして、それぞれ「右」、「左」という切り分け方があるのは周知だとおもうが、本書は、それぞれ「右」と「左」を規定した政治理念が形骸化をむかえ、73年を転機に、それとは別の、「自由」と「安定」の政治理念がねじれたかたちで競りあがってきたのではないか、という提起をなすっている。背景としては、現代を席巻してゆくグローバリゼーション、新自由主義の潮流をあとづけようとするのが本書の目的かえ。「右」と「左」が「反近代」というバージョンを伴っている指摘は、おもしろい。2012/08/12