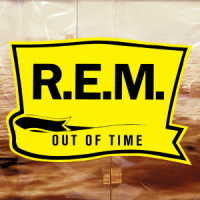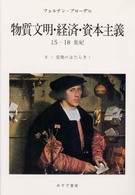内容説明
「法則」や「理論」の本当の意味って知ってる?「科学的な説明」って何をすること?「科学」という複雑な営みはそもそも何のためにある?素朴な疑問を哲学的に考察し、科学の意義とさらなる可能性を対話形式で軽やかに説く。科学の真理は社会的構成物だとする相対主義に抗し、世界は科学によって正確に捉えられるという直観を擁護。基礎から今いちばんホットな話題までを網羅した、科学哲学入門の決定版。
目次
1 科学哲学をはじめよう―理系と文系をつなぐ視点(科学哲学って何?それは何のためにあるの?;まずは、科学の方法について考えてみよう;ヒュームの呪い―帰納と法則についての悩ましい問題;科学的説明って何をすること?)
2 「電子は実在する」って言うのがこんなにも難しいとは―科学的実在論をめぐる果てしなき戦い(強敵登場!―反実在論と社会構成主義;科学的実在論vs.反実在論)
3 それでも科学は実在を捉えている―世界をまるごと理解するために(理論の実在論と対象の実在論を区別しよう;そもそも、科学理論って何なのさ;自然主義の方へ)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
71
科学哲学の入門書。先生と生徒二人の鼎談形式であまり馴染みのない科学哲学の論議を分かりやすく解説していくが、再読が必須と思われる。科学の歴史から、科学自体の認識や考え方を哲学として考えていくのだが、様々な理論があり感心しつつ楽しんだ。先日読んだ、オカーシャの『科学哲学』で説明不足に感じた、社会構成主義のことが簡潔に説明してあり納得。こっちを先に読んだほうが良い。一般的に哲学や思想というと思いつく名前は出てこないが、新鮮で明快なアイデアに驚き、それをこの薄い本にまとめる著者に感心する。おすすめ。2018/02/03
inami
28
★3.5 「科学」と「哲学」のコラボとなれば読まない訳にはいかない(笑)。その昔ライプニッツもデカルトも科学者(17世紀に科学者という言葉はなかった)であり哲学者でもあったわけで、世界を理解(明らかにする)するため活動をしていた。本書では、まず科学哲学とはなんぞや、目指しているのはどういうことかという説明から始まり、科学方法論ということで、演繹や帰納などに触れる。様々な「〇〇論」が登場するが、科学は直接に観察できない対象(電子など)について正しいことを言えるとは限らないという「反実在論」も・・そうくる 笑2023/07/07
ころこ
27
本書でいう科学とは理系のことです。今日、文系に位置付けられる哲学にとって外部にある科学をどう文系の体系に位置付けるかは難しい問題です。3部構成中の第2部から科学哲学の問題がはじまります。第1部は論理学なので、ピンとこなかった読者は2部から読むとかみ合うかも知れません。科学の知識は必要ありません。第2部では科学的実在論と反実在論の立場をたたかわせています。著者は科学的実在論の立場ですが、決定不全性の問題は思弁的実在論と同じ問題の所在なので、反実在論を推したくなります。奇跡論法に代表される素朴な実在論は、実の2018/12/28
seki
26
戸田山先生の専門である科学哲学論に関する本。学生と著者自身であるらしい大学教師の対話形式となっており、とっつきやすいが、やはり内容は難しい。科学と哲学。昔は同じ学問領域だったものが、今は切り離されているが、人間の眼にはなかなか見えないものと格闘しているという点では今も同じだろうというのが私の理解。科学哲学というのは、科学が真理へ迫る際にその橋渡しを哲学によって行うものらしい。帰納、演繹など論理学で多用される言葉が本書でいくつも登場する。科学は実験などだけでなく、こうした方法で磨かれていくようだ。2021/02/28
マウリツィウス
21
【科学哲学史】ライプニッツ以降近世化された「思想」像はモナドロジーによるキリスト教領域との共振で「科学化」、継続することで思想転換を導いてきた。空間様式とその追究課題に意味を要し、現代思想以降の新規学問と定義可能だ。「科学史」=通時/「科学哲学」=共時関連項を解析するならば近代科学像とはパラダイム転換で発生したいわば「現代思想支柱」に過ぎず、それを従来形式と原型へと逆転させる方法論に「科学哲学」を見出せる。論理記号学ではなく思想界におけるパラダイム考察に重要意味を有し、科学の始原と誕生を意味する典型学説。2013/06/23
-
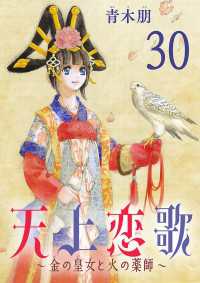
- 電子書籍
- 天上恋歌~金の皇女と火の薬師~【分冊版…