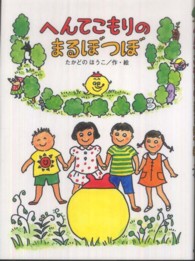内容説明
クラシック音楽は、いつからか「癒しの音楽」と喧伝されるようになったが、その王道は「怖い音楽」に他ならない。父、死、神、孤独、戦争、国家権力―。名だたる大音楽家たちは、いかにこれらの「恐怖」と格闘し、稀代の名曲を作り上げてきたのか。モーツァルトからショスタコーヴィチまで、「恐怖」をキーワードに辿る西洋音楽の二〇〇余年。
目次
第1の恐怖 父―モーツァルトによる「心地よくない音楽」の誕生
第2の恐怖 自然―ベートーヴェンによる「風景の発見」
第3の恐怖 狂気―ベルリオーズが挑んだ「内面の音楽化」
第4の恐怖 死―ショパンが確立した「死のイメージ」
第5の恐怖 神―ヴェルディが完成した「宗教のコンテンツ化」
第6の恐怖 孤独―ラフマニノフとマーラーの「抽象的な恐怖」
第7の恐怖 戦争―ヴォーン=ウィリアムズの「象徴の音楽」
第8の恐怖 国家権力―ショスタコーヴィチの「隠喩としての音楽」
著者等紹介
中川右介[ナカガワユウスケ]
1960年生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。出版社アルファベータを設立し、代表取締役編集長(~2014年)として、音楽家や文学者の評伝などを編集・発行。自らもクラシック音楽、歌舞伎、映画などの分野で旺盛な執筆活動を続ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
流之助
16
「怖い」の感覚は人それぞれではあるが、この本では楽曲の何が怖いのかをその時代背景を中心に書いている。モーツァルトからショスタコーヴィチまで、全作曲家を網羅することは無理であっても、音楽史を通じて何の影響を受けてその曲が作られるに至ったか、思いをめぐらせながら読んだ。作中に列記された楽曲をYouTubeで再生しながら少しずつ読み進めたが、やはり名曲。聞き惚れて読み進められないことも多かった。2023/08/30
toshi
12
怖いというよりも不協和音などで不快な気持ちにさせたり、マイナーで暗い曲調の作品を切り口にした音楽史。 あまり恐怖ということにこだわらないで単純に作曲家の物語として楽しく読める。2016/03/07
Syo
11
実は、クラシックにも 何度、挑戦したことか。 マイブームも 何度もあるんだけど…。 ちょうど、レイザーディスク のライバルのオフコースの 解散コンサートを思い出し、 楽天でDVDを買ったとこ。 アマデウスも 持ってるのよねぇ。 の、モーツァルトから。 あぁあれね。 で、ベートーベン。 田園ね。 なるほどね。2016/05/04
マカロニ マカロン
8
個人の感想です:B+。クラシック音楽は「癒し系」と言われるが、実は「地震、雷、火事、親父」に代表される怖いものをテーマにしたものが多い。戦争や死は大きな主題でもあった。モーツァルトの『ドンジョバンニ序曲』から始まり、ベートーヴェン『田園』、ベルリオーズ『幻想』、ショパン、マーラー、ワーグナー、ヴェルディの『葬送』や『レクイエム・怒りの日』等など、YouTubeで曲を確かめながら読んでいくと、今まで何気なく聞いていた曲に潜む『怖さ』に気付かされた。また、作曲家の生涯や恋愛、病、死という生涯も興味深く読めた。2016/12/11
Decoy
7
中川右介による、ものがたりで読む音楽史。いつもながら、すこぶる付きの面白さ。“怖い”がテーマでありながら、著者もあとがきで書いているとおり、「きわめてオーソドックスな音楽史」になっているところが興味深い。とはいえ、ヴォーン・ウィリアムズやブリテンに多く紙幅が割かれていたり、ショスタコーヴィチでまるまる1章使っているあたりは、独特かも。2016/05/05