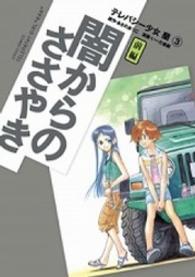内容説明
ウクライナ危機を発端とする深刻な米ロ対立は、このまま「第二の冷戦」を生んでしまうのか?元ソビエト大統領のゴルバチョフを筆頭に、元ホワイトハウス報道官のフィッツウォーターから、元フランス大統領補佐官のアタリまで―。世界史を変えた男たちが集い、冷戦終結の舞台裏を明かすとともに、いま出来しつつある危機の深層を解きあかす。不毛な国際対立を終わらせるための警告の書!
目次
第1章 ウクライナ危機への警鐘
第2章 「対話」の始まり―ゴルバチョフ登場とジュネーブ会談
第3章 突破口となった「決裂」―レイキャビクとワシントン
第4章 冷戦はいかに終結したか―ヤルタからマルタへ
第5章 ヨーロッパの分断克服に向けて
第6章 ドイツ再統一とソビエト崩壊
第7章 新たな冷戦は避けられるか?
著者等紹介
山内聡彦[ヤマウチトシヒコ]
1952年生まれ。NHK解説委員(旧ソ連、南アジア担当)。東京外国語大学卒業後、NHKに入局。ウラジオストク支局長、モスクワ支局長などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 3件/全3件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
James Hayashi
29
当時の米ソのトップ、レーガンとゴルバチョフの交渉を再現。米、仏、独の高官とゴルビーのインタビューを交え、40年に渡る冷戦を終結させた外交の舞台裏を見る。ゴルビーが考慮されていたのは、1)冷戦により突出した軍事費により国内経済疲弊。2)軍拡競争に歯止め。3)東欧への不干渉、鉄のカーテンの撤廃、ヨーロッパとの交流。4)ドイツ統一と同盟(NATO)への参加への可否など。ゴルビーにより社会主義国の壁が崩れるという歴史的瞬間を見る事ができた。しかし、ソ連の経済と安全保障は屑となり、ソ連崩壊、ゴルビー辞任へ 続く→2019/07/11
1.3manen
24
実務優先せず、会議成果を後回しにし建前に固執。細部の詰めができないソビエト。官僚制が持つ、 現況を顧みない弊害(77頁)。いけない。 東西ドイツ統合において、国民が統一したいという希望を持っていたこと。ロシア人もドイツ人もそう 思えることでした(ゴルビー218頁)。新しい協力の道を探り始めたのに、アメリカは態度硬化。 アメリカの帝国を作ろうという考え(235頁)。いかんね。 難しい舵取り。プーチン大統領は大丈夫だろうか? 2015/05/29
モリータ
14
◆2015年3月刊。'14年2月のウクライナ騒乱とクリミア危機、それに続くウクライナ東部での戦争により表面化した露と欧米の深刻な対立。その打開のために学ぶべき歴史として、冷戦終結時の東西首脳の歩み寄りの過程を、ゴルバチョフを始めとした米独仏の当時の高官へのインタビューから振り返る。NHKの番組の内容を再構成したもので、著者2名は制作スタッフ。◆柔軟かつ真摯な姿勢で外交交渉に臨んだゴルバチョフのリーダーシップや人柄の反面、内政・経済面でコントロールに失敗し支持を失った過程、当時のソ連の状況にも興味は持続。2021/09/29
coolflat
7
冷戦終結に多大な役割を果たしたゴルバチョフが語る冷戦終結史とロシアの今後。ソ連書記長に就任したゴルバチョフは「新思考外交」と呼ばれる新しい概念を打ち出す。主な内容は、核兵器の大幅削減など全人類的な利益をイデオロギーよりも優先する事、欧米諸国との関係を改善し、東欧諸国に対しても内政に干渉せず、主権を尊重することなどだ。それにより米国とはINF全廃条約等、核兵器削減に貢献し、欧州では、ブレジネフドクトリンの放棄により、東欧諸国の民主化の動きを促し、ドイツの再統一においては、統一ドイツのNATO加盟を容認する。2015/08/22
tsubomi
6
2017.03.27-04.17:ウクライナとロシアの衝突の解決方法を探るべく、米ソの冷戦終結への対話と駆け引きとを、当時の関係者へのインタビューを素にして浮き彫りにした内容。ウクライナ問題に関しての内容は薄いですが、冷戦終結のプロセスは非常にわかりやすいです。ゴルバチョフさんは笑顔が穏やかそうで、社交的で、好印象を抱いていたものですが、実際に彼と接した多くの人も、私と同様の意見だった模様。晩餐会が重要な役割を果たしていたのは興味深いです。制裁は緊張をもたらすだけだという言葉が印象的。2017/04/17
-

- 和書
- 優しい傷 文春文庫