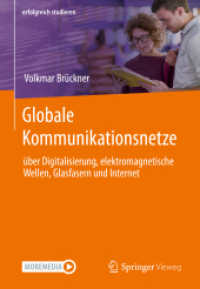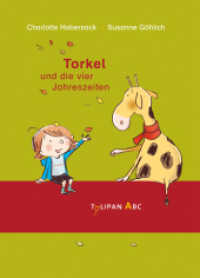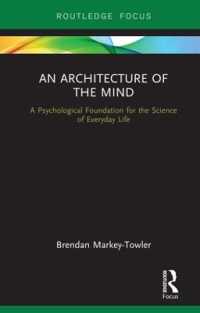内容説明
資源枯渇と魚価安で、衰退の一途を辿る日本の漁業。既得権でがんじがらめの「水産ムラ」にいまメスを入れなければ、漁業者の暮らしは救われず、食卓から国産の魚が消える日も近いだろう。しかし、適切な資源管理と健全な組合経営で、日本は世界有数の豊かな漁業と海と食卓を取り戻せる―。改革派の旗手が三陸復興へ思いを込めて描く、持続的で儲かる漁業の未来図。魚の放射能汚染についても解説。
目次
序 いま漁業を改革しなければ、日本の魚は食べられなくなる
第1章 三陸漁業者はいま―変わり果てた海を前に
第2章 花形産業から斜陽産業へ―日本漁業の近代史
第3章 儲かる漁業の方程式―先進国に学ぶ改革モデル
第4章 漁業は自己改革できるか―デタラメ経営との決別
第5章 新しい水産モデルを三陸から―産業とコミュニティ再生への提言
第6章 水産物の放射能汚染について最低限知っておきたいこと
著者等紹介
勝川俊雄[カツカワトシオ]
1972年東京都生まれ。三重大学生物資源学部准教授。専門は水産資源管理と資源解析。東京大学農学生命科学研究科にて博士号取得。東京大学海洋研究所助教を経て現職。日本水産学会論文賞および日本水産学会奨励賞を受賞。研究の傍ら、政策提言のほか、漁業者や消費者とともに持続可能な水産資源管理や漁業の制度改革に向けて活動を行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
よーこ
11
日本の漁業が抱える問題点を分かりやすく示した良書。日本人の漁業へのイメージと現実は大半が異なっている。まず日本人の「魚離れ」が取りだたされているが、実際は世界第2位の魚好き国家であること。そして日本の漁業の衰退は、後継者不足以上に、乱獲による国産魚の枯渇が原因であること。日本の漁師は乱獲などしない(近隣国家の問題)と思われているが、政府が規制をしないばかりに、稚魚を獲り尽くしている状態であること。全くの知識ゼロから読んだが驚かされた。日本人はイメージではなく、まず現実を知らなくてはならないと強く感じた。2017/10/14
poku
7
勝川さんの本です。 自分も漁業方面の分析を始めるまではにほんがまさか魚の資源管理の点で世界的に遅れていること、乱獲が「日本の漁業者」によって行なわれていることを知りませんでした。報道は中国や韓国の密猟者の話ばかりですから。2015/08/28
ume 改め saryo
7
後半の放射能汚染についてがとても参考になりました。 情報をどう扱えば分らなかったり、考え方そのものが日常生活に活かせます。 ベクレルとシーベルトの違いや、食べていいものの基準の考え方や、年間の被ばく量なんかです。 読んで良かった(^^)2012/10/25
ぼや
5
日本漁業の問題と提案が、分かりやすく紹介されている一冊。利益の出ない乱獲を続けてしまう漁師たちの上部組織である漁協ひいては水産庁の責任は重い。合わせて、本書に取り上げられたような内容が、正しく報道されず、人々が関心を持ちにくいことも問題に思う。一消費者としての選択肢が少ないだけに、どうすれば良いか悩ましい。2017/10/14
keepfine
4
ノルウェーの成功例を参考にした政策誘導と漁協の改革。法規制による乱獲の抑止は、資源保全としての側面とともに、経済性もある。すなわち短期的な漁獲量は落ちるが、中長期的には成長した魚を獲ることにより単価が上がり、持続可能な漁業につながる。2018/01/01