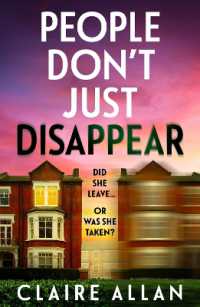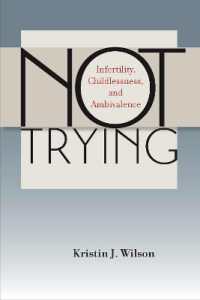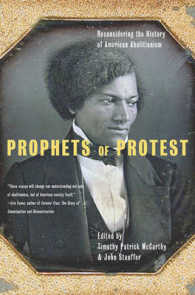内容説明
「このままやっていてもなあ…」と何となく感じるとき、人は新たな能力を生み出す局面をむかえている。「がんばっている自分」にはまることなく、人間に本来備わっているはずの「飽きる力」をどう目覚めさせ、活用すべきなのか。身体論、システム論の地平を拓く哲学者が「努力していることの疲れ」を纏うすべての現代人のために贈る、心と身体のリハビリの書。
目次
序章 疲れた生活を変えるために
第1章 飽きること
第2章 飽きながら育つ
第3章 何に私は飽きたのか―オートポイエーシスとの出会い
第4章 飽きることができない日本
第5章 一生懸命であることに飽きる
第6章 「間違った努力」に飽きる―リハビリの現場から
終章 飽きるための簡単なエクササイズ
著者等紹介
河本英夫[カワモトヒデオ]
1953年、鳥取県生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。現在、東洋大学文学部哲学科教授。オートポイエーシス・システムという次世代型のシステム論の開発、改良を行い、精神病理学、アート、リハビリテーション、進化論といった多くの現場とコラボを組みながら展開を続けている。ことに身体論、発達論、現象学で固有の展開が多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
-

- 電子書籍
- 永遠の一夜【分冊】 11巻 ハーレクイ…