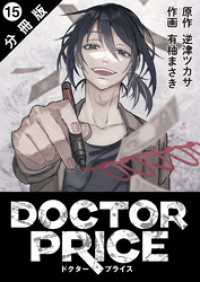内容説明
二〇一〇年は、平城遷都からちょうど千三百年目に当たる年。奈良の寺院と深い交流を持ち、実際の仏像制作や保存修復に携わる名うての彫刻家であり、さらには「平城遷都一三〇〇年祭」のマスコットキャラクター「せんとくん」の生みの親でもある著者が、「奈良のみほとけ」を訪ねながら、その仏像から派生する彫刻技法や作者の思い、時代背景を縦横に見る。仏像から日本の仏教、果ては日本人のこころに迫った会心の書。
目次
プロローグ 奈良のこころ、ほとけさまのこころ
第1章 ほとけの来た道
第2章 ひかりのほとけさま
第3章 漆でできたほとけさま
第4章 木彫仏は揚子江から
第5章 南部復興を支えた仏師たち
第6章 仏像の技法研究と修復―私とほとけさまと人材育成
エピローグ 日本人にとっての仏教、そしてほとけさま
著者等紹介
藪内佐斗司[ヤブウチサトシ]
1953年大阪市生まれ。彫刻家。東京藝術大学美術学部彫刻科卒業。同大学大学院美術研究科修了。同大学大学院保存修復技術研究室助手時代の経験で得た古典技法をもとに、仏教的世界観や東洋的自然観を独自の造形で表現。2004年より、東京藝術大学大学院文化財保存学保存修復彫刻研究室の教授に就任。代表作に「童子」作品。第二一回平櫛田中賞ほか受賞多数。平城遷都一三〇〇年祭のマスコットキャラクター「せんとくん」の生みの親(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さつき
67
せんとくんは大好きで色々グッズも持っています。著者がその生みの親だとは知らずに読み始めましたが、良い本に出会えました!!仏像の種類や時代ごとの様式、様々な素材、技法で作られたその製作法も図で表されていて、とても分かりやすいです。仏教が伝播した飛鳥時代から鎌倉時代まで、どのような歴史背景のもと、人々は仏像にどんな願いを込めてつくったのか。人から人へ受け継がれたその思いの熱さに心が震えます。いつかまた奈良に行きたいです。2020/04/19
pdango
55
★★★★★ふと思いたって中宮寺の如意輪観音を見に。「寺社巡り」「御朱印集め」や「パワースポット巡り」ときいてもピンとこなかったのに、「仏像に会いに行く」は何故かしっくりきた。『見仏記』のぶっとんだかんじもいいけど、彫刻家目線で熱く語っているこちらを読むと、ほんとにほんとに、是非、本物(仏像)を見に行かねば!という気持ちになる。新しい楽しみが見つかった(^-^)2020/01/22
mackey
2
「せんとくん」の生みの親で、彫刻家の著者によって、奈良の仏像の技法や歴史的背景について深く描かれている。奈良のお寺巡りの前に読んでおくと、一味違った目線で、楽しめそう!2015/02/27
nizimasu
2
仏像は日本の美術の中心でもあり、信仰の対象でもあった。なぜ、ぶつぞうがこれほどまでに広がりがあり、多様なのか。その秘密を歴史的にたどっていくのが本書。これまたわかりやすさでは、抜群で何とも読んでいて仏像を見るのがますます楽しくなりそう2011/12/21
Michio Arai
1
奈良の仏像に特化しているところが気にいった。 筆者の籔内は東大寺の金剛力士像の作者運慶に対して強い尊敬の念を持っていて、その熱い語りにこちらも引きこまれます。それにしても金剛力士が3000もの部材の組み合せで出来ているとはすごい。もはや一つの建築物ですね。 東大寺、興福寺、広隆寺、薬師寺、唐招提寺、聖林寺、飛鳥寺、当尾の里の岩船寺に浄瑠璃寺、みんな行ったとこばかり。新薬師寺と白毫寺に至っては、つい先日すぐそばを通っている。仏像も一通り拝観しているが、この本をハンドブックにもう一度見て回ろうかと思います。2016/12/19