内容説明
混迷する現代日本を考えるとき、おなじような混乱の時期を乗り越えて、力強い歩みを見せた明治以後の仏教の歴史は示唆に富む。廃仏毀釈、キリスト教・西洋思想の流入を前に仏教者はどう立ち向かったのか。新たな仏教の再構築に苦闘した先人たちの思索と実践の跡をたどり、仏教の本質と未来に生きる指針を探る。
目次
第1章 明治の仏教弾圧事件
第2章 仏教の本質を求めて
第3章 原語習得の苦難
第4章 宗派の教学の新展開
第5章 研究条件の整備
第6章 思想家の仏教観
第7章 結び
著者等紹介
田村晃祐[タムラコウユウ]
1931年茨城県生まれ。東京大学文学部卒業。文学博士。東洋大学文学部教授を経て、現在、東洋大学名誉教授、東方学院講師。日本印度学仏教学会賞、日本印度学仏教学会鈴木学術財団特別賞、中村元東方学術賞受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はるたろうQQ
1
廃仏毀釈など仏教排撃の流れを前提に、明治以降の代表的仏教者の生き方や考え方を概観する。その意味では纏まった読みやすい本。ただ、はじめにやあとがきで著者は現代の日本は道徳が崩壊していると批判し仏教を始めとする宗教による道徳の復活を期待するが、違和感がある。戦前の各種宗教教団の戦争賛美は勿論のこと、現在のロシアとロシア正教会の関係やイスラム教とアラブ諸国の関係を観るに、安易に宗教に期待すべきではないだろう。古い考え方だが、国家とは別にある社会の基本的なルールや考え方として蓄積されていく道徳の形成に期待したい。2023/08/14
なむさん
0
なかなかの良書だなと感じました。『望月仏教大辞典』や『織田仏教大辞典』を手にする前に、井上円了や鈴木大拙、和辻哲郎といった人々の著作にふれる前に、さらっと一読してみるのはいかが。
-
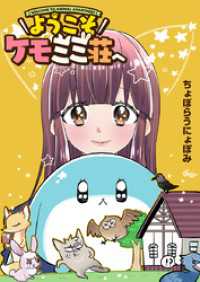
- 電子書籍
- ようこそケモミミ荘へ【タテヨミ】10 …
-
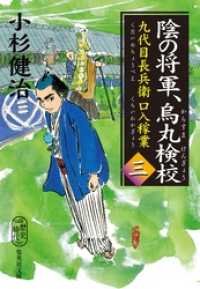
- 電子書籍
- 陰の将軍、烏丸検校 九代目長兵衛口入稼…







