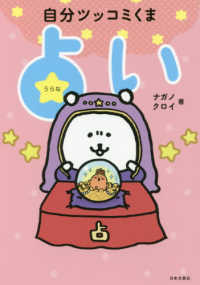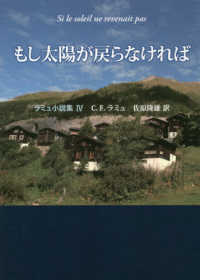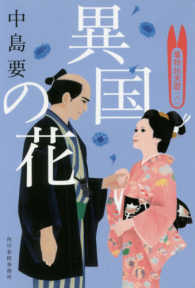内容説明
ゆかりの各地を訪ねて今に残る風景や暮らしを見つめ、良寛・一休の実像に迫った紀行文学の名作二篇を収録。貧困や腐敗が横行する現世を飄々と生きながら、人々の心をとらえて離さない和尚たちの葛藤や心のつぶやきを海鳴りの浜辺で、古堂の軒先で、街路のかたすみで聞く。
目次
良寛を歩く(哀しき娘たち―木崎;石が語るもの―木崎;娘らの里へ―分水町;名主の息子―出雲崎 ほか)
一休を歩く(生誕地付近―嵯峨野;求法、求師の道―京都;蒼顔放浪―京都;大死一番―大津 ほか)
著者等紹介
水上勉[ミズカミツトム]
1919年、福井県生まれ。11歳の時に得度するが36年に還俗。翌年、立命館大学文学部国文科に入学し、すぐに中退。生業のかたわら文筆活動を続け、48年刊の『フライパンの歌』がベストセラーに。50年代末から話題作を次々と発表し、60年代には人気作家として不動の地位を築く。61年『雁の寺』で直木賞、75年『一休』で谷崎潤一郎賞、84年『良寛』で毎日芸術賞を受賞
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroki Nishizumi
1
導入は越後から来た上州木崎宿の薄幸な飯盛女たちの墓石を訪ねるところから入る。一貫して、ただ良寛の光の面のみを伝えるのではなく、時代の闇を映そうとする姿勢が著者らしく、素晴らしい。 「飢饉の年は飢饉の米を、豊作の年は豊作の米を人にめぐまれて、雀にもまいておられたにちがいない。…」 「なにごとも みなむかしとぞ なりにける はなになみだを そそぐけふかも 良寛」 いずれ出雲崎や寺泊の良寛ゆかりの地を訪ねたいものだ…2012/05/31
ダージリン
0
新潟に住み数年。良寛を少し知ろうと思って読んだのだが、ゆかりの地を歩き、思いを馳せるという本書のスタイルはなかなか味わいがある。死の間際に貞心尼と交わした「うらを見せ おもてをみせて ちるもみぢ」という歌はグッときた。2010/10/20