内容説明
1964年の東京オリンピックは、体育の時代の象徴だ。教育の名のもとに横行する「体罰=暴力」の連鎖を止めるには、暴力の否定から始まったスポーツの本義を理解する必要がある。その出発点となるのは、2020年東京オリンピックにほかならない!
目次
序章 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック招致成功!
第1章 体育の時代への決別 スポーツの時代への期待
第2章 スポーツの視点から見た体罰問題
第3章 「スポーツとは何か」をもう一度考える
第4章 柔の道―日本のスポーツを柔道の歴史を通して考える
著者等紹介
玉木正之[タマキマサユキ]
1952年京都府京都市生まれ。スポーツライター。現在、桐蔭横浜大学客員教授、静岡文化芸術大学客員教授、石巻専修大学客員教授、立教大学大学院非常勤講師、立教大学非常勤講師、筑波大学非常勤講師などを務める。「日本初」のスポーツライターとして数々のスポーツ競技・選手を題材にルポ、評論などを執筆。ジャズ、クラシック、オペラなどの音楽評論や小説も手掛け、現役の指揮者・金聖響との共著もある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こも 旧柏バカ一代
13
私は著者の玉木正之氏のファンです。 毎週月曜日の氏がアンカーをするニューズ・オプエド を見てます。 氏が常日頃言ってる事が文字になったのが本書。 スポーツは体育ではなく遊戯である。 体罰はスポーツの理念から最も遠い存在だと再認識。 後半は、柔道の成り立ちと嘉納治五郎の功績が書かれていて、現在の日本柔道がいかに理念から遠のいたか書かれていた。 むしろフランス柔道の方が嘉納治五郎の理念に近いかもしれない。2019/09/01
たろーたん
2
そもそも、スポーツ指導をするのに罰など必要ないはずである。そして、体罰は互い対等の関係で起きるのではなく、先生と生徒という上下関係がある状態で行われる。その点で体罰は権力を通した・使った暴力である。それなのに、体罰の議論では常に「体罰はどこまで許されるのか」という「量」に関する議論になる。量ではなく、権力を通した暴力行為だから問題なのだ。そして、一発ビンタで生徒がシャキッとするかもしれないが、そんな一時のカンフル剤が人生と言う長い期間有効に作用するはずがなく、さらには量も増えていくのだから良いはずがない。2023/06/16
山口透析鉄
2
市の図書館より本を借りて読破。正直、その後の醜態の限り(森喜朗や高橋晴之等のざま)を見るに、東京五輪再度招致おめでとうの文章は玉木正之さんらしからぬ駄文に堕していて、後々の「ビクトリースポーツ」というスポーツニュースアプリ(残念ながらサービスは終了しているようです)での批判インタビュー記事につながっていたのでしょうが、あとの文章は概ね良かったですね。 体罰と体育会からはもう何も生まれないです。日大理事長等の醜態に直結していますよね。インタビュー記事は本日、私のTweetに再録しておきましたよ。(10/2)2022/09/03
-
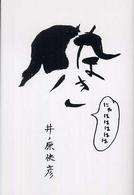
- 和書
- イノなき







