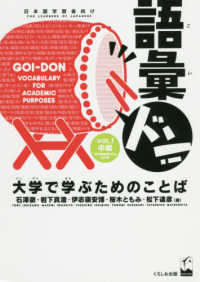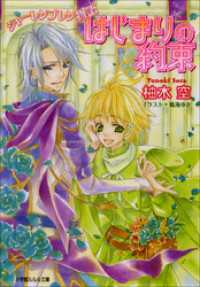内容説明
「経済外交」とは―経済的“利益”を追求する外交ではない、経済を“手段”とする外交である。TPP問題の底流には、戦後日本が選んだ「経済>政治」の決断があった。「政治」を捨て、「経済」を選んだ―その理由とは。
目次
第1章 アジアと太平洋のはざまで―アジア通貨危機の勃発によりAPECが目指す自由貿易圏構想は瓦解した。なぜ、アジアと太平洋の連帯が図られたのか
第2章 環太平洋連帯構想の誕生―環太平洋連帯構想の理念、それは「緩やかな開かれた連帯」にあった。なぜ、経済優先の国際協調が進められたのか
第3章 経済援助積み残された課題―日韓基本条約によって日本は韓国への戦後賠償を経済援助と置き換えた。なぜ、戦後日本の外交は経済を重視したのか
第4章 アジア・アフリカ会議と日本―アジア・アフリカ会議で日本は「経済」という新たなツールを見出す。政治問題を忌避する外交の始まりでもあった
著者等紹介
井上寿一[イノウエトシカズ]
1956年東京都生まれ。学習院大学法学部教授。一橋大学社会学部卒業。同大学院法学研究科博士課程などを経て現職。法学博士。専攻は日本政治外交史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takizawa
6
湾岸戦争の際の巨額の資金協力は評価されなかった。アジア通貨危機では二国間関係に基づいて経済援助を行ったが,資金提供以外の繋がりを持てないでいる。歴史を遡ると,OECD加盟により先進国の仲間入りを果たした日本は,国際会議や二国間協議を通じてアジアを支援することで自信を深めていた。1950年代には国連加盟とAA会議への参加を両立し,対米協調とアジア地域主義との間でバランスを取った。歴史的・文化的背景がバラバラなアジアは経済的な結びつきが重要。アメリカを含む形でバイからマルチへ。この辺りが歴史から学べる教訓。2012/10/28
ブナ太郎
4
なぜ、アジア太平洋は一つになれないのか。その理由が考察されている。時代を“遡る”という特殊な構成のため、番組を観ていないと分かりにくい部分がある。そこは注意が必要だ。日本は少なくとも60年代までは単なるアメリカ追随外交ではなかった。外交の方向性が混迷する今の時代。この時代から学ぶべきことは多いと感じた。2012/11/10
Kazuo
2
アジアという概念そのものがヨーロッパを起源とするものであり、我々「アジア人」が「アジア人」を意識すること自体が、現時点では不可能である。日本のアジア外交は、過去、明(中国)冊封体制の中にあり、現在はアメリカ冊封体制の中にある。本書によれば、菊池清明は「少なくとも60年代までは、日本の外交というのは対米協調一点張りということじゃなかった」と強調している。当然ながら、日本のアジア外交の目標を「設定/常に修正」し、実行し、検証すべきは、アメリカではでなく、日本人自身である。日本人自身とは貴方と私のことである。2015/04/19
1.3manen
2
TPPでアジアとの経済連携、自由化、通商国家。一方、反対派は分断、アメリカ化、対米従属(8ページ~)。今日の選挙結果でTPPもどうなるか、ほぼ方向性が判明する。文字が大きく読みやすい本。大来佐武郎氏。この人を初めて知ったのは、ODAの卒論を書いていたときであった(83ページ~)。「開かれた連帯」、「開かれた地域主義」を今日、どう捉え返すべきなのか。さらに遡って、徳川鎖国時代のトラウマがこういう呼称となったのか。遡って今の原因を究明する手法は、歴史研究のみならず、自省を込めて必要な未来への展望の前提である。2012/12/16
yasu7777
0
★★★☆☆2017/09/23