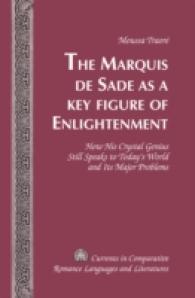内容説明
歴史には時代の流れを決定づけたターニングポイントがあり、それが起こった原因を探っていくことで「日本が来た道」が見えてくる。朝廷と決別をはかった武門の覇者―彼らはいかにして「真の統治者」となりえたか。1392年→1336年→1253年→1180年と“学び”によって成長した武士の姿を見る。
目次
第1章 足利義満「日本国王」の権力―1392年(明徳3年)(公家を遇して武士の成熟をはかる;公家を凌駕する存在へ;「祭祀権」と「課税権」を奪う;なぜ相国寺は御所の北につくられたか;「象徴天皇制」をつくった男)
第2章 足利尊氏「京都」に挑む―1336年(建武3年)(得宗専制と幕府の揺らぎ;御家人の不満が幕府を倒した;時代錯誤の新政と武士の不満;武士の意を汲んだ反逆;尊氏がとった「京都」という選択;足利尊氏の光と影)
第3章 北条時頼万民統治への目覚め―1253年(建長5年)(武士は危険な収奪者だった;支配して気づいた己の未成熟さ;統治者への道を示した「御成敗式目」;時頼の「撫民政策」の背景;貴族には生まれなかった撫民という「思想」)
第4章 源頼朝「東国」が生んだ新時代―1180年(治承4年)(「イイクニ」つくろう?;暴力装置としての武士;清盛が先鞭をつけた武家政権;頼朝の挙兵と武家政権の誕生;「源平合戦」ではない;「武士の都」鎌倉;主従関係の整理と朝廷との決別;武士の「学び」とは)
著者等紹介
本郷和人[ホンゴウカズト]
1960年東京生まれ。東京大学史料編纂所教授。東京大学文学部卒業後、同大学大学院で石井進氏・五味文彦氏に師事し、日本中世史を学ぶ。専攻は日本中世政治史・古文書学。文学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
樋口佳之
アキ
takizawa
amabiko
Go Extreme