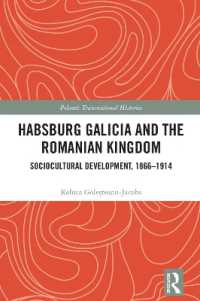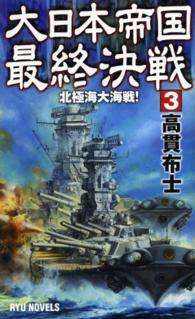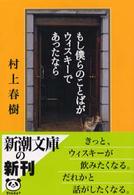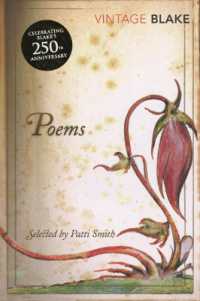内容説明
歴史には時代の流れを決定づけたターニングポイントがあり、それが起こった原因を探っていくことで「日本が来た道」が見えてくる。急速な近代化を果たした明治期の日本―その国家運営の中核を担ったのが「官僚」だった。1889年→1881年→1873年→1871年の指導者の“信念”に裏打ちされた政策を見る。
目次
第1章 帝国憲法・権力の源泉―1889年(明治22年)(官僚と官僚制;個から組織へ;伊藤博文の欧州「憲法調査」;太政官内閣から近代内閣制へ;国家の「須要」に応える帝国大学;大日本帝国憲法と行政;その後の官僚たち)
第2章 十四年の政変・近代化の分岐点―1881年(明治14年)(土蔵に眠る憲法;よろしく内治をととのえ国力を養う;自由民権の季節;豪農と学術講談会;大隈重信と福沢諭吉;明治十四年の政変;近代化の方向と速度)
第3章 巨大官僚組織・内務省―1873年(明治6年)(役所のなかの役所を率いた男;明治六年の政変;内務省設立;産業振興プロジェクト推進本部;殖産興業事業;士族の反乱;大久保の悲劇)
第4章 岩倉使節団・近代化の出発点―1871年(明治4年)(二つの国家的課題;岩倉使節団の使命;全権委任状をもっているのか;イギリスが富強であるゆえん;近代化路線の確定;意見を届ける)
著者等紹介
佐々木克[ササキスグル]
1940年秋田県生まれ。京都大学名誉教授・博士(文学)。立教大学大学院博士課程修了。京都大学人文科学研究所助教授を経て1988年に同研究所教授。2004年に京都大学を定年退職後、11年3月まで奈良大学教授。日本近代政治史を専門とし、とくに大久保利通の研究で知られる。著書に『大久保利通と明治維新』(吉川弘文館、吉田茂賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
takizawa
ブナ太郎
ごる
takuchan
きらきらり