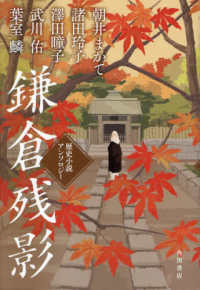目次
1 知識経済が未来の富を生む(「第三の波」と社会の変化;手法としての未来学;知識が主役の新たな経済;変わりつつある時間の概念;官僚機構の限界点;グローバル化の課題)
2 ものづくり大国・日本の未来像(「第二の波」と「第三の波」の衝突;変革へ向けた日本の課題;研究開発と人材の交流)
3 パワーストラクチャーと国際間の協力(アメリカ中間選挙以降の変化;危険度を高める極東アジア;世界から孤立する中東;イラク、そして中東の未来;NGOが果たす役割)
4 「生産消費者」が変化をもたらす(新たなパワー「生産消費者」;未来をひらく生産消費者;新時代へ向けた教育の課題;新しい教育の実験;科学技術の発展と人間の未来;「人間」を再定義する;21世紀を切りひらくキーワード)
インタビューを終えて 未来社会に到来する「波」
著者等紹介
トフラー,アルビン[トフラー,アルビン][Toffler,Alvin]
1928年生まれ。未来学者。トフラー・アソシエイツの共同創設者で、経済、科学、社会を中心に広くグローバルトレンドについて執筆・講演活動を行う。1970年に刊行された最初の著作『未来の衝撃』以来、『第三の波』『パワーシフト』と次々に世界的なベストセラーを送り出す。変化の背後に潜む新たな潮流を探り出し、それを理解するための知的枠組みの構築が一貫した著作のテーマ。最新刊の『富の未来』では、「生産消費者」という概念で、これまであまり論じられなかった非金銭経済が、新しい知識社会の中で果たす役割について、広範な例をあげて論じている。ワシントンのアメリカ国防大学の教授、国連女性開発基金米国委員会の共同議長を兼任
田中直毅[タナカナオキ]
1945年生まれ。東京大学法学部卒業後、東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。現在、国際公共政策研究センター理事長。国民経済研究協会主任研究員を経て、1984年より本格的に経済評論活動を始める。郵政民営化委員会委員長をはじめ、政府税制調査会、金融審議会、財政制度審議会など多数の政府審議会委員を歴任。1997年からは21世紀政策研究所理事長に就任。2007年4月より現職。『最後の十年日本経済の構想』(日本経済新聞社)で第10回吉野作造賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
halaryo@いつもココロに青空を
030314
クスモク
さんちゃん
mochi_u
-

- 和書
- 女の110番