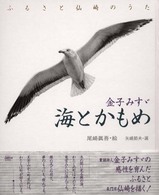内容説明
学級崩壊、不登校、いじめ、キレる子現象、援助交際…。これらはどれも、行き詰まりをみせる日本型社会システムからの「逃走現象」といえまいか。子どもも、親も、教師も―みんなこの社会に溺れかかっているのだ。小学生から大学生までを対象にした意識調査を比較分析。子どもたちの「今そこにある危機」を読み解き、世紀末日本の在り方を問い直す。
目次
1 わがままってステキ(バタフライナイフの意味するもの;「いきなり」と「普通」 ほか)
2 偏執蓄積型社会からの逃走(学校か警察か;学級崩壊という名の逃走 ほか)
3 自立できない子どもたち(赤信号の無視をめぐって;自己コントロール ほか)
4 若者たちの仕事観(会社から逃走した若者たち;大学生の職業意識 ほか)
5 子どもたちの目覚め(自由を求めた二つの試み;教師という権力 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kenitirokikuti
5
図書館にて。2000年刊行。〈援助交際が子どもたちの間で広がったのは、伝言ダイヤルやテレホンクラブ、デートクラブという通信手段によるところが大だ。〉千石の職歴に東京地検検事。やっぱ法務の役人的な考えだと思う▲『「まじめ」の崩壊』(サイマル出版、1991)について、あるアメリカの学者から批判を受けた。千石は日本がポストモダンの状態にあるというが、誤っている。日本人にはポストモダンの前段階であるところのモダンがないのだ、と。こういう昔の日本異質論って懐かしいねえ。2021/05/23
まるっちょ
2
「自分の存在を認めてもらいたい一方で、社会には無関心」という一見矛盾とエゴが生じそうなこの言葉が私たちの世代を言い表しているように思える。昔よりも仕事に対する執着が無くなった。「面白いか、否か」で仕事を選ぶ若者たち。価値観は変わるものだというが、果たしてここまで変わっていいものか。2015/07/08
鑑真@本の虫
0
ちょっと分析不足かな? まぁ、悪くはなかった。2012/12/03
-

- 電子書籍
- 仕事中、だけどやめないで。【マイクロ】…
-

- 和書
- 花翻訳者