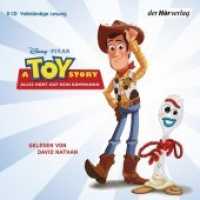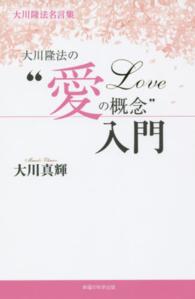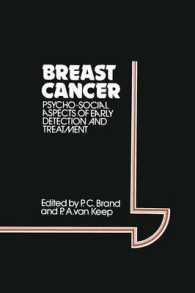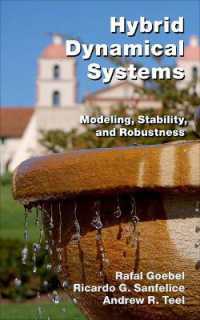目次
第1章 心を形にする(定型の基本;作歌の基本 ほか)
第2章 表現を磨く(演出―上手な嘘をつく;展開―思い切って飛んでみる ほか)
第3章 作歌問答・ここが知りたい、短歌の急所(題詠の楽しさ;写生の魅力 ほか)
第4章 実作の現場―作品の適否を考える(カルチャーセンターの短歌講座;文学館主催の短歌講座 ほか)
著者等紹介
三枝昂之[サイグサタカユキ]
1944年山梨県生まれ。早稲田大学入学と同時に早稲田短歌会に入会。96年「りとむ」主宰。現代歌人協会賞、若山牧水賞、芸術選奨文部科学大臣賞、斎藤茂吉短歌文学賞、現代短歌大賞などを受賞。2005年から二年間「NHK短歌」選者をつとめる。歌会始選者でもある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たんぽぽ
16
ここ数年、日曜朝のNHK短歌をよく視聴している。共感したり、心に響いたりする歌との出会いがあって興味を持っているが、読む時は勿論、自分がもし歌を詠む場合にも心得とか知っておいた方がいいだろうと思って、去年図書館で借りて読んだ。「短歌は人間の体温にもっとも近い詩型」という。「すぐれた歌は表現量に過不足がない」。確かに心のゆらぎが素直に、シンプルに、ストレートに伝わってくる歌に惹かれる。決まった表現量からの言葉の力を感じたいからかもしれない。私もささやかな日常や「暮らしの中の特別な日、節目」を詠えたらなぁ。2021/11/21
Gamemaker_K
10
「悲しい」という気持ちを表現するとき、「万人の悲しさ」ではなく「あなたの悲しさ」をしっかりと表現すること・・・というのは作文でもよく言われる。でもそれを短歌で実行するとなると難しい。適当な言動を減らすこと、使える言葉を増やすこと、どっちも大切だなとさらにスタートラインが遠ざかったような気分になったりして。でもまあ「作る投げる叩かれる」の手順を踏まないといけないわけでもあるので、あまりグズグズするのもいかんな、とも思ふ。2015/01/24
Koning
6
NHKの短歌講座番組の選者?の本。現代的な発表するつもりの短歌のお約束という感じでしょうか。手前勝手に作ることは時々やってたんだけど、こういうのも読んでみるべーと(w。読み終わるとやっぱり手前勝手にやっていこうと、安心できたので、こういうのもいいのかもしれない(え2013/02/17
905
3
いろいろ盛りだくさんだけど、「すぐに忘れてしまうような気分や出来事も、歌に詠むことで暮らしを豊かにしてくれる」みたいな窪田空穂の見解が印象に残った。2022/04/28
ルート母
0
短歌を自分で作る事と出会ってやっと1年の私にとって、どの章も為になることばかりでした。一度読んだだけで実践できるわけではないですが、いくつかだけでもこれから活かしたい。2025/10/07