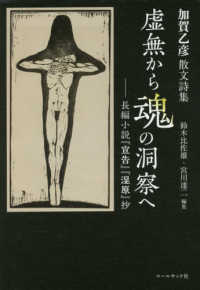- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 構造主義・ポスト構造主義
内容説明
世界が現象する瞬間へ!すべてが痕跡であり「読み」によって現象するのなら、そのつどの「読み」の正しさは、どこに求められるのか?デリダの世界認識の深奥に迫る野心的試み。
目次
1 脱‐構築とは何か(差延;反復;脱‐構築)
2 なぜ脱‐構築は正義なのか(痕跡を「読む」とは;反復の不安定性;生き埋めにされた不在のもの ほか)
3 秘密、あるいは証言(正義はつねに秘されたままにとどまる;切迫した「決定」ないし「決断」;不可能な決定に身を投ずる ほか)
著者等紹介
斎藤慶典[サイトウヨシミチ]
1957年横浜生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程修了。慶應義塾大学文学部哲学科教授。哲学博士。専門は、現象学、西洋近・現代哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 地方消費税の経済学