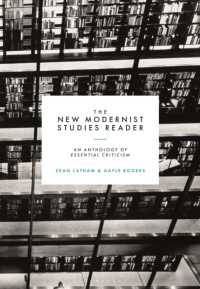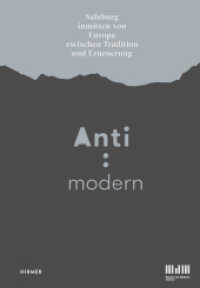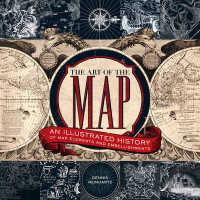内容説明
銅鐸三九個が、神々の棲む出雲・加茂岩倉でみつかった。これら史上最多の弥生時代の祭りのカネ=銅鐸は、果たして出雲でつくったのか、それとも近畿でつくったのか。いつ、誰が、何のために埋めたのか。一三年前に発掘された神庭荒神谷の銅剣三五八本との関連はあるのか。古代出雲には、強大な勢力をもつ「王国」「地域国家」があったのか。本書は、銅鐸研究のオーソリティである二人の考古学者が、発見から現在までのプロセスを追い、銅鐸たちの「すがた」と「かたち」を考究しながらさまざまな観点と論点を提起し、青銅器文化の深層に迫る同時進行ドキュメントである。
目次
1 銅鐸発見
2 加茂岩倉遺跡
3 現地にて
4 岩倉の銅鐸
5 さまざまな解釈
6 銅鐸の絵
7 生産地はどこか
8 ×印のある銅鐸
9 古代出雲と銅鐸・銅剣
10 自然銅説の崩壊
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちー
2
出雲の岩倉遺跡で見つかった多数の銅鐸。その発見を受け考古学(特に銅鐸など の祭具)を研究している春成氏と佐原氏が対談という形でその出土・形などを様々な角度から検証していく。……といっても検証していく様そのものを記述しているため、最終的に銅鐸が何故で作られたかまでは至っていない。現在では研究が細分化していくため、その研究者自体が限られてくる。普通の本では論ありきで対照的な論は否定されやすいが、研究者がそれぞれに論じていくために極一的な論じ方はなされていない。世紀の発掘に胸踊る研究者の高揚感が伝わってくる。2013/01/16
takao
1
ふむ2021/03/24
海辻
1
1996年に出雲の加茂岩倉遺跡で発見された39個の銅鐸。2人の考古学者が、地質・製銅・分析など数々の専門家の意見を取捨選択しながら銅鐸の謎を解こうとしてます。最終的には「完全な正解は霧の向こう」という形ですけど(笑) ただ佐原氏の語る実験考古学の怖さは納得。「現代の技巧を駆使しても石型で銅鐸が作成出来ないからといって、安易に『土型で作ったに違いない』と断定できない。古代の技術の方が優れていた場合もありうるのだから」。ごもっともです。(図)2010/03/29