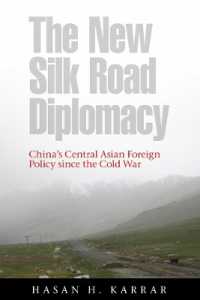内容説明
食卓を彩る小品の文化誌。「何はなくとも香の物」―漬物は、日本人の食卓に欠かせない小さな名品であり、丹精を込めて仕上げる味の芸術である。神代の昔から食されていた漬物は、長い間の生活の知恵に育てられ、その土地の気候風土を反映して、今日の多種多様なものとなった。では、時代の移り変わりのなかで、漬物はいかにその姿と味を変えてきたのか。これからはどのような漬物が望まれるのか。長年、漬物の低塩化に取り組んできた著者が、日本の各地方に伝わる名産の数々と、古来からの漬物と日本人の関わり、漬物の科学を誌しながら、この「小さな芸術」の奥の深さを明らかにする。
目次
第1章 漬物紀行
第2章 漬物の歴史
第3章 漬物の科学
1 ~ 1件/全1件
- 評価
稲岡慶郎の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さっちも
13
日本の食文化の変遷における漬物の変化、東アジアとの比較、世界の食文化における日本の漬物のあり方、漬物の化学、栄養素と多岐にわたる内容。仏教文化の流入により肉食を避け、菜食中心の生活になった為、漬物の酸味を好まない傾向が強いという。肉食の油や生臭さを消す必要がないからだ。逆に梅干の強酸は健康の為、薬用の為に拡がったという見解。また、料理の調味料として漬物を使う文化が少なく、漬物単体で食べる事が多いのが特徴ということ。漬物が浸かる過程で起こる浸透圧や乳酸発酵、アルコール発酵の仕組みも理解できなるほどの連続。2022/02/06
-
- 洋書
- Kringle
-
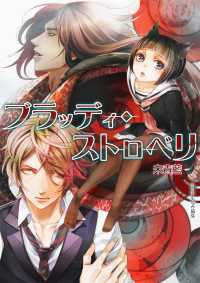
- 電子書籍
- ブラッディ・ストロベリ アプリーレ文庫