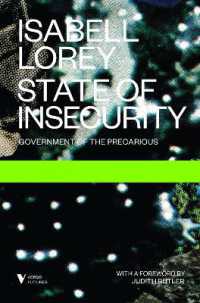出版社内容情報
世界的言語学者が、言語の思考規定説を否定し、人類普遍の心的言語の存在を明かす。又、人は生来、諸言語に共通する文法の基本原理を本能レベルでもつことを裏づける衝撃の書。
内容説明
母語が思考を枠づける、とするサピア、ウォーフの言語決定論を実証的にしりぞけ、言語本能説の前提として、人は普遍的な心的言語で思考することをまず洞察する。さらに、文法のスーパールールが生得であること、その基本原理を幼児は母語に応用して言葉を獲得することを、最新の発達心理学等から確認する。チョムスキー理論をこえて、人がものを考え、言葉を習得し、話し、理解するとき、心の中で何が起きているかを解き明かす、アメリカで大きな反響をよんだベストセラー。
目次
1 技能を獲得する本能―言語本能
2 おしゃべり―ヒトのあるところ、必ず複雑な文法あり
3 思考の言葉―心的言語
4 言語の仕組み―生得のスーパールール
5 言葉、言葉、言葉
6 サウンド・オブ・サイレンス
7 トーキングヘッズ―文を理解する心的プログラム
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
absinthe
128
言語に関して、世間の誤解をぶった切る。古い言語の理論を論破する姿は痛快。言語は親が教えるものではなく、子が再発明するものだというのに納得。また、サピアウォーフ仮説のおかしさを完全に論破する。チョムスキーの言語理論は、大学の言語学ですでに学んでいたので違和感なく受け入れる事が出来た。チョムスキーはチューリング機械との関連で切り離せない人だ。absintheの生涯ベストの中の1冊。
かんやん
32
音声を使ってコミュニケートする動物を観察してみれば、人間の言語が本能由来だと言われても違和感はない(厄介なのは本能という概念を表すのも言語だから)。言葉はなくとも思考は成り立つのは、たとえば道具を使用して課題をクリアする類人猿を見ても分かる。本書では、知的障害を伴わない言語障害や、言語障害を伴わない知的障害が例に上がる。更にはイメージ思考など。言語が文化や発明でなく、先験的なものならば、あらゆる言語に通底する普遍的な文法が心的に存在することが推定される。チョムスキーの「原理とパラメータ理論」である。2020/12/19
tom
23
椋田直子さん翻訳の「言語が違えば、世界も違って見えるわけ 」が面白かったので、同じく椋田さん翻訳のこの本を読むことにした。出版当時に買って、以来27年、捨てられずに書棚の肥やしにしていた本。言語学にはなんとなく興味があり、この本の冒頭にはチョムスキーのことが書いてある。この本でチョムスキーのことが分かれば、嬉しいなあという気持ちもあった。でも、結論からいうと難解。分からないところ、面倒なところは投げ飛ばして読み進める。言語は、頭の中にあるのだ。どうもそうらしい。せっかくここまで読んだのだから下巻に進む。2022/07/03
白義
18
人間は、誰かに教えられなくても無限に新しい言葉を産み出す能力を身につけるように育つ。そうした無限の言語を産み出す、本能に刻まれたルールである「文法」がどんなもので、どう人は身につけるのか、その全貌を平易に解説した記念碑的一冊。恐らく最良のチョムスキー言語学入門だし、またその建設的な批判、発展ともなっている。上下巻の大著だがその内容は言語学の全域に及び、しかも一貫した視点で統一されているので明晰だ。おまけに既存の言語に関する議論に挑発的で、それがいいフックとなって一気に読ませてくれる。ピンカーの名声の始まり2018/04/15
まふ
11
上巻は言語の構造を英語をベースに分析する。いわば英文法の精密編のようなもの。人間のどの言語も動詞、名詞などの語素は同じであり、並び方、使われ方が異なる。これは人間が生まれた時から本能として持っており、後天的に覚えるものではない。これを普遍文法(Universal Language)と名付ける。というのが言いたいこと。2020/11/11
-

- 電子書籍
- エリートジャック!!(12) ちゃおコ…