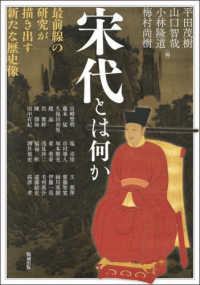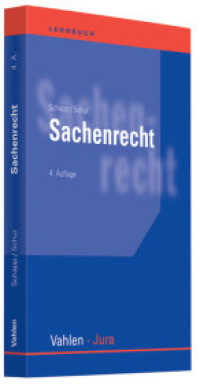内容説明
子どもの願いを無視して、大人が一方的に発達課題を強制すると歪みが生じやすい。日々、保育の実践にたずさわる著者は、一見、理解しがたい幼児の遊びや描画を、子どもの世界の表現とみることによって、その心を理解する。本書は、子どもと共生しつつ子どもの世界が育つのを見守る真摯な保育論。従来の発達心理学がきり捨てた子どもの生きた姿を捉える人間学的児童心理学の新しい試みである。
目次
第1章 描画と子どもの世界―理解しがたいことを理解する過程(子どもの世界の発見;子どもの体験が表現される描画;人間の表現;描画にあらわれた対極のイメージ;個性を発揮しつつ共生すること)
第2章 遊びと子どもの世界―理解しつつ共生する過程(子どもの生活に参与すること;子どもの世界に出会う―表現としての理解;子どもとの生活を形成すること―保育の現在的性格;自己実現の体験の欠如から生じたと思われる行為;省察における理解)
終 人間学的児童心理学へ
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
陽子
29
前半は子どもの描く絵を分析しながらの実際。描く行為を「心の表現の表れ」と見て、生活全体の中から「子ども像」を読み解いていく見方に感嘆。後半は障がい児とのやりとりの中で、真に「子どもの世界をどうみるか」。行為を表現としてみること。大人の常識的規範に当てはめると、子どもの心が見えなくなることがあるんだなと改めて思った。どんな行為にも寄り添い、最後まで見届ける忍耐力と分析力に敬服の思いだった。自身を顧み驕ることなく誠実に、どんな子に対しても同じ目線に立とうとする著者の姿勢に感銘した。2021/08/04
shinobu
1
1960年代から児童心理学者として保育の現場にいる著者による、子どもの視点に寄り添った解答のない、保育の実践書。前半は数年に渡り、1人の子どもの描画からその子の『虚の自己実現』を読み解き、後半は養護学校での障碍児保育の実践について読み解いていく二部構成。子どもの視点に立つと、大人の論理の無意味さと子どもの自由さがよくわかる。なかなか難しいことではあるが、ぜひ試してみたいと感じる良書。自分が生まれるより昔からこのような保育方針の人が存在したことに驚きつつも敬意を表する。2010/09/18
Keyhei
0
子どもの行為をどのように捉え解釈していくのか,また捉え方をどのように反省するのか,具体的な事例で書かれている。幼児や児童に限らず,他者を理解しようとする際のよく観察することや丁寧に考えることの難しさと大切さを考えさせられた。2017/08/09