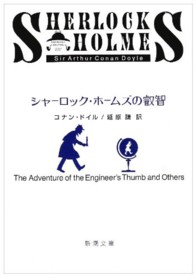出版社内容情報
定評ある辻日本美術史の補訂版.縄文からマンガ,アニメまでを視野に入れ,日本美術に変わらずあり続ける特質を大胆に俯瞰する.最新の研究動向をふまえて記述をアップデート,よりわかりやすく解説.重要な作品を加えてさらに充実したニューバージョン.オールカラー.【東京大学出版会創立70周年記念出版】
内容説明
縄文からマンガ・アニメまで、第一人者による書下し通史。最新の研究動向をふまえて記述をアップデート、収録作品もさらに充実。オールカラー。
目次
第1章 縄文美術―原始の想像力
第2章 弥生・古墳美術
第3章 飛鳥・白鳳美術―東アジア仏教美術の受容
第4章 奈良時代の美術(天平美術)―唐国際様式の盛行
第5章 平安時代の美術(貞観・藤原・院政美術)
第6章 鎌倉美術―貴族的美意識の継承と変革
第7章 南北朝・室町美術
第8章 桃山美術―「かざり」の開花
第9章 江戸時代の美術
第10章 近・現代(明治‐平成)の美術
著者等紹介
辻惟雄[ツジノブオ]
1932年愛知県生まれ。1961年東京大学大学院博士課程中退(美術史専攻)。東京国立文化財研究所美術部技官、東北大学文学部教授、東京大学文学部教授、国立国際日本文化研究センター教授、千葉市美術館館長、多摩美術大学学長などを歴任。現在、東京大学・多摩美術大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
風に吹かれて
15
以前読んだ辻氏の『奇想の系譜』がすこぶる面白かったので、同じ著者の本書を手に取った。通史のような本は教科書的で読む意義はあっても退屈してしまうことがあるが、本書も期待にたがわず面白かった。「かざり」「あそび」「アニミズム」を鍵に日本美術を活写。 どの時代も面白いし、今日に至る日本の美術の多様性を改めて認識した。 いつ見ても何度見ても感に入るのは縄文・弥生・古墳の時代の人々が手作りした作品の数々。芸術と認識して作っていたかどうかは別にして、日々を生活し生きる中で制作された数々の美しさは何とも言えない。 →2025/03/31
takao
1
ふむ2023/04/02
hi
0
縄文土器・弥生土器に関する解説が、最新の研究成果を反映していない印象を受けました。出版時期を考えると仕方ない面もありますが、このテーマに関心がある方は、より新しい研究書と併せて読むことをおすすめします。2025/08/31
Chisaka
0
縄文から現代までの日本のARTについてわかりやすく事例を交えながら解説してくれた本。これは一冊あるとよいですよ2021/07/01
kaz
0
時代は弥生から現代まで、範囲は絵画等から工芸品、建築までと幅広く、圧倒される。飛鳥時代から鎌倉時代くらいまでの仏像の変遷、建築様式の歴史的変遷、近代の絵画の変遷等、何らかのテーマを決めて眺めても面白い。渡邊翁記念会館が堂々と掲載されているのも嬉しい。図書館の内容紹介は『「かざり」「あそび」「アニミズム」をキーワードとして、絵画、彫刻、工芸、考古、建築、庭園、書、写真、デザインなどの多分野にまたがる日本美術の流れを、縄文から現代までたどる。最新の研究動向を踏まえた補訂版』。2021/08/13
-
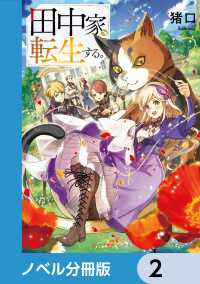
- 電子書籍
- 田中家、転生する。【ノベル分冊版】 2…
-
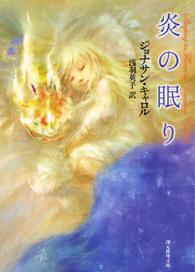
- 和書
- 炎の眠り 創元推理文庫