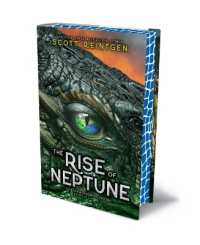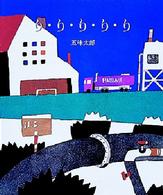出版社内容情報
明治期に創立された三崎臨海実験所は、世界でも最も歴史の古い臨海実験所のひとつとして、日本における生物学の発展に大いに貢献してきた。近代日本の幕開けから現在にいたるその歩みを丁寧に振り返りながら、今後の海洋生物学研究・教育拠点としての実験所の展望を示す。
目次
第1章 明治期の三崎臨海実験所(1886‐1912年)
第2章 大正期の三崎臨海実験所(1912‐1926年)
第3章 昭和期の三崎臨海実験所(1926‐1989年)
第4章 平成期前半の三崎臨海実験所(1989‐2004年)
第5章 平成期後半から令和期の三崎臨海実験所(2005年~現在)
第6章 相模湾の豊かな生物相とその保全―三崎臨海実験所周辺
第7章 三崎臨海実験所人物記
第8章 日本の臨海実験所の未来への歩み
著者等紹介
森澤正昭[モリサワマサアキ]
1942年栃木県日光に生まれる。現在、東京大学名誉教授。専門分野:動物学、発生生物学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
志村真幸
1
東京大学三崎臨海実験所の歴史をまとめた一冊だ。 第13代所長を務めた森澤正昭さんが発足から平成期前半までを、第15代所長の岡良隆さんら4名が平成期後半から令和期までを担当執筆している。 敷地の選定、諸施設の建設、船舶の建造、歴代所長たち、式典やイベント、出席者、会議や計画のあらましといったところが中心。研究施設としてのハード面が詳しくわかる。 採取された生物や研究についてもふれられているが、人名や生物名くらいで、つっこんだ内容ではない。そのあたりに期待している読者は、拍子抜けするかも。2024/03/10