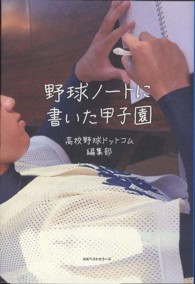出版社内容情報
インターネットはモバイルで人をつなぎ、さらにモノをつなぐことにより(IoT)現代のインフラとなった。技術の進歩とコロナ禍の経験は、いま都市を「場所のインターネット」へと変貌させつつある。インフラと法、人々の行動と参加、創造性や文化まで、学際的研究によりその実態と可能性を描き出す。?? ?
内容説明
物理的空間と社会経済活動の関係が緩み、ダイナミックにつなぎ直される時代に、物理的都市はデジタル空間との競合・共存にどのように取り組んでいくべきか。今後の都市の課題や進むべき道を各分野のエキスパートたちが考察する。
目次
第1部 序論(インターネット・オブ・プレイスの概念)
第2部 社会経済レイヤー(都市と地方の二元論を超える;エモーショナルな都市―人々は都市に何を求めているのか? ほか)
第3部 文化レイヤー(イノベーションの新たな文化を育む「場」のデザインとその戦略;都市にとって美とは何か?―ビッグデータとAIを用いた「感性的なもの」の定量化の試み ほか)
第4部 データ/技術レイヤー(都市におけるデータプラットフォームとイノベーション;エリアマネジメントのDXがもたらす都市の拡張 ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kthyk
16
60年代、ビートルズの「レットイットビー」やピーター・クックの「インスタント・シティ」、それが東京における情報時代のはじまりだったと教えられたことがある。そして60年、インターネット真っ盛りの「トウキョウ」論。具体的には「秋葉原」と「大手町」。読書会のお誘いがあり、速読した。ポイントは題名にある「プレイス」。コロナ禍後の都市を単なる「スペイス」ではなく、いかに意味ある「情報都市」にするかにある。構成は8人の論者の論文集。内容は具体的ではあるが全ては技術論。都市は人間が生み出すもの、と考える小生は食傷した。2023/10/27
Go Extreme
1
https://claude.ai/public/artifacts/9b2b6823-404c-449b-9539-b408ef457fed 2025/06/24
ハヤシコウダイ
0
コロナを経てリモートが普及し「どこでも住める時代」となった。しかし、どこでもがゆえに「どこで住むか」が曖昧になってしまい、そこに住む理由を考える段階に突入した。2024/08/08